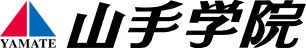自分を鍛える冬
Winter’s strength
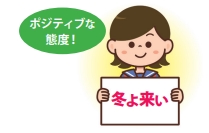
冬は厳しい。春の温かさ、夏の暑さ、秋の涼しさ、そして、冬の寒さ。人にとって、寒さはもっとも生命に関わる。それでも、その冬をもっとも好んだ詩人がいた。冬の詩人といわれる高村光太郎(1883-1956)だ。国語の教科書に、「道程」や「ぼろぼろな駝鳥」や「レモン哀歌」が採用されているので、君たちも彼の詩を読んだことがあるだろう。とくに「レモン哀歌」は、世界の名詩に比肩する絶唱だと思う。
詩集『道程』から「冬が来た」を引用してみよう。
「きっぱりと冬が来た/八つ手の白い花も消え/公孫樹の木も箒になった/
きりきりともみ込むような冬が来た/人にいやがられる冬/
草木に背かれ、虫類に逃げられる冬が来た/
冬よ/僕に来い、僕に来い/僕は冬の力、冬は僕の餌食だ/
しみ透れ、つきぬけ/火事を出せ、雪で埋めろ/刃物のような冬が来た」
この詩を読んだ君は、高村光太郎の確固たる態度を発見するだろう。厳しい冬を描きながら、光太郎のポジティブな態度は揺るがない。彼は、冬を嫌がらない。彼は、冬から逃げない。冬の厳しさを力にして、冬の厳しさを自分のエネルギーに変える。
君が受験生なら、「高村光太郎も受験生で、この詩の冬は、受験の比喩(隠喩)かも」と感じるかもしれない。詩は、読者の感性で読み解くものであるから、この詩の「冬」を「受験」や「試練」に置き換えて読むのもおもしろい。「わたしは受験を嫌がらない。わたしは受験から逃げない。受験の厳しさを力にして、受験の厳しさを自分のエネルギーに変える」と考えても、詩の趣旨から外れるわけではない。「冬が来た」は、そのままの冬、と読むこともできるし、比喩(隠喩)として、読むこともできる。
高村光太郎の伝記を知ると、たとえば、「僕の前に道はない/僕の後ろに道は出来る/ああ、父よ/僕を一人立ちにさせた父よ/僕から目を離さないで守る事をせよ/常に父の気魄を僕に充たせよ/この遠い道程のため」(初出より引用)の父は、実父の高村光雲(上野公園の西郷隆盛像や重要文化財「老猿」の作者)とも読めるし、もっと大きな存在の比喩(隠喩)として読むこともできる。
ところで、態度には、目標(対象)がなければ、ポジティブも、ネガティブもない。目標が設定されて、はじめて態度が決まる。もし、君に目標がなければ、受験も試験もそれほど気にならないだろう。高村光太郎には、芸術という目標があったから、「冬(試練)が来た」となるのだ。目標に対して、「前向きに取り組む」なら、ポジティブな態度になり、取り組みを避けるなら、ネガティブな態度になる。
君が自分の目標を実現したいなら、君はポジティブな態度を選ばなければならない。
ポジティブな(積極的な)態度を選んで目標を実現するか、それともネガティブな(消極的な)態度を選んで目標をあきらめるか。
さあ、冬が来た。自分の目標に全力で取り組もう!
山手学院 学院長 筒井 保明
山手学院 50 周年。これまで、ホットラインや小冊子やイベントなどを通じて、学習方法や学習習慣のつくり方などをアドバイスし、みなさまとともに実践してきました。また、中学受験、高校受験、大学受験に関する情報や精細なデータに基づく入試分析などを発信し、受験校選択や受験学習に活用してきました。
学習や生活や受験に関する知識や情報を広く知らせることは、生徒や保護者のみなさまの気づきや発見を促し、今後の学習や生活や受験に必ず役立ちます。
ぜひ、山手学院こども教育研究所のメールマガジンをお申し込みください。(週 1 回の定期配信と教育情報の号外配信になります)
●メールマガジンご登録フォームはこちら
自分の価値
Your Self-Worth

君は、自尊心を持っているだろうか。
文字どおり、「自分を尊重する気持ち」である。自尊心は、プライドでも、うぬぼれでも、独りよがりでもない。ただ、「自分を大事にすることができるかどうか」だ。
いうまでもなく、君は、自分を大事にしなければならない。自分を大事にする人が、自分の目標を達成する人である。
ところが、何人もの生徒たちと話していると、「あれ。自分を大事にしていないな」と感じることがある。
何時間も集中して学習していた事実に感心して、
「よくがんばった。家に帰ったら、お風呂に入って、リラックスしてから、ぐっすり眠るんだぞ」
と声をかけると、
「ぼくは家に帰ったら、ゲームをします」「ぼくはスマホをチェック」「わたしもスマホ」「わたしはユーチューブを見ます」
それぞれ笑顔で答えてくれる。
ときどき、「ぼくは宿題」「わたしは復習」という返事があるけれど、「ゲーム」「スマホ」「ユーチューブ」などが圧倒的に多い。
もちろん、怒りはしないが、やさしい口調で、
「今日、いままでの学習は、短期記憶として海馬に蓄えられている。家に帰って、リラックスして眠れば、その短期記憶が長期記憶として定着する。宿題や復習は、繰り返しになるから、問題ないけれど、ゲームやスマホやユーチューブは、新しい情報として、学習の定着の妨げになってしまう。せっかく何時間も学習したのに、もったいないじゃないか」
と諭すことになる。そして、どの生徒も理由はわかってくれるが、問題は、家に帰ったあと、かれらがゲームやスマホやユーチューブなどの誘惑に打ち克てるかどうか、ということだ。
何時間も学習したのは、自分の目標を達成するためだろう。自分の目標を本当に大事に考えているなら、誘惑に負けてはならない。しかし、人はそんなに強くない。保護者に協力してもらって、家庭でのゲームやスマホやパソコンの使用ルールを決めたり、保護者に預けたりすることが必要かもしれない。
まず、君は、自分の目標に対して、自分は目標に値する価値がある、と確信することだ。そうすれば、数々の誘惑を退けることができるようになる。自分の価値を自分で評価することを英語でセルフ・エスティーム(self-esteem)といい、いちばん近い意味の言葉が「自尊心」だ。自分を尊重することは、自分を高く評価することにほかならない。
自分を尊重できれば、君の自己イメージが高くなる。そして、自己イメージが高くなれば、君は自分の能力を発揮できる。学業でも、スポーツでも、芸術でも、自己イメージの高い人が成功している。なぜなら、目標の達成を邪魔する余計な誘惑に負けることがなくなるからだ。
君の価値は、ほかでもない、君自身が決めるのだ。英語で、I’m Worth It! わたしにはそれだけの価値がある。
自分と自分の目標を大事にしよう!
山手学院 学院長 筒井 保明
山手学院 50 周年。これまで、ホットラインや小冊子やイベントなどを通じて、学習方法や学習習慣のつくり方などをアドバイスし、みなさまとともに実践してきました。また、中学受験、高校受験、大学受験に関する情報や精細なデータに基づく入試分析などを発信し、受験校選択や受験学習に活用してきました。
学習や生活や受験に関する知識や情報を広く知らせることは、生徒や保護者のみなさまの気づきや発見を促し、今後の学習や生活や受験に必ず役立ちます。
ぜひ、山手学院こども教育研究所のメールマガジンをお申し込みください。(週 1 回の定期配信と教育情報の号外配信になります)
●メールマガジンご登録フォームはこちら
君の本来の能力
Your Ability by Nature

いま、ここに君が存在している以上、君のなかに本来の能力がある。
第一に、君は学習能力を持っている。そもそも人が生きるためには学習が必要であり、学習能力は人の行動になって表れる。
毎日の生活を考えてみれば、君は、自分の行動とともに、つねに何かしら学んでいるはずだ。
ただし、その行動が方向性を持っていないと、せっかくの学習が雲散霧消してしまうかもしれない。
毎日の君の行動に方向性を持たせるためには、君自身の目的や目標をしっかりと持つことだ。自分の目的や目標があれば、君の行動や学習は、目的や目標にむかって集合していく。
たとえば、バスケットボールの選手を目指しているなら、野球やサッカーの練習ではなく、バスケットボールの練習をするだろう。そして、毎日の生活のなかで、さまざまなことがバスケットボールにつながっていくだろう。なぜなら、「バスケットボールの選手になる」という目的が、バスケットボールに関連する情報を収集し、自分の行動を導くからだ。
また、志望校合格を目指しているなら、志望校合格に必要な条件を確認して、通知表評定や偏差値や得点などの目標を定めるだろう。当然、学習内容や学習への取り組み方も目標達成につながるものになる。なぜなら、志望校合格という目的が、自分の行動を決定するからだ。
ところで、人を機械のように固定して考える傾向の人たちがいて、人の能力やIQは生まれつき(遺伝)であると主張する。たしかに、ある程度の生まれつきはあるけれど、基本的に、人の能力は環境と取り組み次第で大きく変わるものなのだ。
IQはIntelligence Quotientの略で、知能指数のこと。知能には、流動性知能と結晶性知能がある。かつてIQは生まれつきであって変化しないという主張が一般的であったけれど、現在では、20歳以前はいうまでもなく、大人になっても、トレーニングによってIQを高めることは可能であるとされる。
わたしも認知学者から「IQは生まれつきで変化しない」と学生時代に教わったが、その日その日、その時その時によって知能が変動している実感があったから、「先生の説明は疑わしいな」と思っていた。人の知能や能力は固定できないものだ。
かりに、完全に同等の能力で生まれた二人がいたとする。一方は、まったく教育環境のないスラム街で育ち、もう一方は、優れた教育環境のある住宅街で育った。一方は、ケンカに明け暮れ、もう一方は、読書に夢中になった。はたして、この二人の知能指数はおなじであろうか?
人は、生まれつきの機械ではない。機械は使えば使うほど、消耗し、機能も少しずつ低下していく。しかし、人は、脳も身体も機能も、適切に使えば使うほど、発達していく。自分を取り巻く環境から働きかけられ、環境に反応し、環境から学びながら成長していく。
君には、本来の能力が備わっている。
まず目的・目標を決める。つぎに、目的・目標に必要な環境をつくる。そして、学び方を身につけ、的確な取り組みを実行する。そうすれば、自然に、少しずつできるようになり、日に日に発展していく。
さあ、前進だ!
山手学院 学院長 筒井 保明
山手学院 50 周年。これまで、ホットラインや小冊子やイベントなどを通じて、学習方法や学習習慣のつくり方などをアドバイスし、みなさまとともに実践してきました。また、中学受験、高校受験、大学受験に関する情報や精細なデータに基づく入試分析などを発信し、受験校選択や受験学習に活用してきました。
学習や生活や受験に関する知識や情報を広く知らせることは、生徒や保護者のみなさまの気づきや発見を促し、今後の学習や生活や受験に必ず役立ちます。
ぜひ、山手学院こども教育研究所のメールマガジンをお申し込みください。(週 1 回の定期配信と教育情報の号外配信になります)
●メールマガジンご登録フォームはこちら
夏の大逆転!!
Changeover in Summer

目的志向という言葉がある。英語ではgoal-orientedという。文字どおり、目的(ゴール)に志が向いている状態だ。意識しているかどうかに関わらず、だれでも、目的志向で行動している。実際、生活のあらゆる場面で、目的志向が働いているはずだ。(食事⇒料理、清潔⇒手洗い、宿題⇒学習、など)
エーリッヒ・フロムという思想家が、君は「持つ様式」(to have)で生きるか、「ある様式」(to be)で生きるか、と問いかけた。
ここに一冊の本がある。A君は本棚に収めて、本を持ったことに満足した。いっぽう、B君は本を読んで感動し、目的を意識して行動を起こした。
ここにサッカーボールがある。A君は、新しいボールを持って、ボールを磨いた。いっぽう、B君は、新しいボールでさっそく練習を始めた。
ここに受験の問題集がある。A君は、受験の問題集を持っていることに安心した。いっぽう、B君は、その問題集が志望校合格に役立つと考えて、ただちに取り組んだ。
フロムは、「持つ様式」で生きるとき、人は物に支配され、「ある様式」で生きるとき、人は物から自由になる、という。「持つこと」は、所有であり、受動的。「あること」は行動であり、能動的。
さて、夏は行動の季節である。朝、太陽が力強く昇り、元気よく目覚めることができる。受験生はいうまでもなく、どの学年であっても、この夏、自分自身の「大逆転」を目指してほしい。「大逆転」とは、現状打破であり、新しい自分になることだ。
そのために、「目的志向」を利用してみよう。毎日の手順は、つぎのようになる。
①まず自分の目的・目標を意識する。目的・目標は一つではないから、さしあたって、いまの自分が最も達成したいことを考える。受験生なら、「志望校に合格したい」でいいだろう。スポーツマンなら、「最高の選手になりたい」でいいだろう。分野に関わらず、「〇〇になりたい」でいいだろう。「ある様式」(to be)で生きることが目的志向だ。
②目的・目標を寝る前に意識に上げて、「君はできる」「あなたはもっとできる」と自分に言い聞かせる。(わたしはできる、わたしはもっとできる、でもいい)言い聞かせたら、リラックスして、熟睡する。
③朝起きたとき、目的・目標を意識して、ただちに「やること」を決める。(あるいは何時に「やること」を決める)そして、ただちに(何時に)必ず実行する。(気分がのらなくても、取り掛かること!)これを、毎日、繰り返していると、その行動が習慣化され、効率よくできるようになる。
④夜、寝る前に、強く一回、「できる」「もっとできる」と言い聞かせて、熟睡する。寝るまでの時間帯に、目的・目標につながることを行っていると、その行動と「できる」という意識が睡眠中に定着し、目的志向を強化することになる。
⑤朝起きたとき、目的・目標を意識して、ただちに(何時に)「やること」を決め、必ず実行する。
以上の行為をくりかえしていると、無意識のうちでも「目的志向」が働くようになってくる。受験生なら、いつのまにか受験学習に取り組んでいる。スポーツマンなら、自然に練習に励んでいる。どの分野でも、目的・目標に必要なことを自発的にやるようになる。
夏は、行動の季節だ。自分の目的・目標にむかって、力強く前進しよう。
山手学院 学院長 筒井 保明
山手学院 50 周年。これまで、ホットラインや小冊子やイベントなどを通じて、学習方法や学習習慣のつくり方などをアドバイスし、みなさまとともに実践してきました。また、中学受験、高校受験、大学受験に関する情報や精細なデータに基づく入試分析などを発信し、受験校選択や受験学習に活用してきました。
学習や生活や受験に関する知識や情報を広く知らせることは、生徒や保護者のみなさまの気づきや発見を促し、今後の学習や生活や受験に必ず役立ちます。
ぜひ、山手学院こども教育研究所のメールマガジンをお申し込みください。(週 1 回の定期配信と教育情報の号外配信になります)
●メールマガジンご登録フォームはこちら
目標と希望とねばり強さ
Goal, Hope, and Tenacity
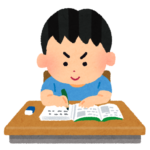
目標の達成に必要なのは、「ねばり強さ」である。そして、「ねばり強さ」の根源は、「希望」である。だから、自分の目標を決めたら、まず強い希望を持って、ねばり強く取り組んでいくことだ。そうすれば、君はきっと目標を達成できるだろう。
「粘り強さ」と聞くと、わたしは、ドイツの詩人、科学者、政治家であったゲーテ(1749-1832)を思い浮かべる。わたしの場合、森鴎外の影響であるけれど、「聖書」の次に重要だといわれた『ファウスト』という作品を例に説明してみよう。
ゲーテ自身の手紙に「20歳のとき、思いついたものを、80歳になって完成させ、発表するのだから、容易なことではない」と書かれている。つまり、『ファウスト』を完成するまでに、60年、かかっている。
森鴎外の『ファウスト考』から引用すると、「ゲーテは満82歳になるまでに、第2二部が脱稿するようにと心掛けた。そして、とうとうその希望を遂げた。(中略)第二部を書くようになってからは、毎日、朝早く、眠りの後に、気分が爽やかに、強くなっていて、まだ日常生活の醜い姿が心を乱さないうちでなくては、出来ない。それも原稿一ページが、珍しく出来の好い時で、ふだんは手の平でおおわれるほどの行数しか書けない。それよりも少ない時もある」
手の平でおおえる行数は、ノート1ページの三分の一程度。そして、それより少ないときもあったのだから、どれほどの「ねばり強さ」が必要であったか、想像できるだろう。
ゲーテは、歴史上、最高の勉強家の一人であった。主人公のファウスト博士には、ゲーテ自身が投影されている。ゲーテ以前のファウスト博士と悪魔メフィストフェレスの契約は「なんでも自由にできる期間を与えよう。ただし、期限が来たら、おまえの魂は悪魔のものだ」であったけれども、ゲーテのファウストとメフィストフェレスの契約は、「向上の知識欲を捨てて、受容(学習)に満足したとき、つまり、みずから向上心を捨てたとき、おまえの魂は悪魔の手に落ちる」というものだった。このとき、契約は試験になった。ファウストは、学び続けることによって、この試験に合格しようと努力した。
たしかに、ファウストがいうように、「人は努力するあいだ、迷うに決まったもの」である。けれども、学び続けるかぎり、ファウストは、悪魔の試験に負けない。
ファウストは、高い努力を続けた。そして、彼は亡くなる間際、一瞬、受容(学習)に満足を感じた。そのとき、悪魔は「勝った」と思ったけれど、神の使いの童子は、ファウストの魂に向かって、「あなたは学びました。つぎは、わたしたちに教えてくれますね」といった。目標を達成したのは、悪魔ではなく、ファウストだった。
靄や霧の道(先が見えない道)を進みながら、ゲーテも、ファウストも、けっして希望を捨てなかった。
君の目標が本気のものならば、必ず希望が生まれる。自分の希望を大切にして、どんなことにも、ねばり強く取り組んでいこう。
「目標」「希望」「ねばり強さ」が君の未来を開くのだ。
山手学院 学院長 筒井 保明
今年、山手学院は、50 周年を迎えます。
振り返ってみますと、ずいぶん長いあいだ、教育情報を発信し続けてきました。
生徒や保護者のみなさまの声に耳を傾けながら、ホットラインや小冊子やイベントなどを通じて、学習方法や学習習慣のつくり方などをアドバイスし、みなさまとともに実践してきました。また、中学受験、高校受験、大学受験に関する情報や精細なデータに基づく入試分析などを発信し、各学年の受験校選択や受験学習に活用してきました。
教室では生徒たちとわたしたちが協同して取り組み、ご家庭では保護者の方の協力で生徒一人ひとりが取り組んできました。そして、その成果が、生徒たちの成長として積み上がっています。これからも、生徒や保護者のみなさまの実践と結果のフィードバックにより、よりよい情報や方法が集まってきます。
学習や生活や受験に関する知識や情報を広く知らせることは、生徒や保護者のみなさまの気づきや発見を促し、今後の学習や生活や受験に必ず役立つものであると考えます。
ぜひ、山手学院こども教育研究所のメールマガジンをお申し込みください。(週 1 回の定期配信と教育情報の号外配信になります)
●メールマガジンご登録フォームはこちら
感情を止めて、自分を観る
Restrain Your Emotions and See Yourself.

まず現在の自分のことを考えずに、未来の自分のことを考えてみよう。「明日の自分」のような、近い未来でもいいし、「二年後の自分」「十年後の自分」のような、遠い未来でもいい。そのとき、「自分はどうなっていたいか」と考えてみると、自分のやるべきことが見えてくる。
明日、仕上げた課題を提出して、先生に感心される自分になりたいなら、君はさっそく目の前の課題に取りかかるだろう。二年後、志望校に合格している自分になりたいなら、君はただちに学習に取り組むだろう。
いま、意識した自分がすぐに行動を起こせば、未来の自分(目的、目標)が実現する可能性がグンと高まる。君が目的や目標に向かう行動をすぐに起こすか、どうか。未来の自分は、この決断にかかっている。
少し先、また、かなり先の未来の自分を考えてみる習慣は、君の人生を大きく変化させるだろう。なぜなら、ひとは、思い描いた目的や目標に向かって、行動するからだ。逆に、目の前のことばかりに気持ちをとらわれていると、ひとは目的や目標を失ってしまうかもしれない。
もし、いま、目の前にゲームがあって、すぐにゲームを始めると、提出する課題は後回しになるだろう。また、友だちに誘われて遊んでしまうと、その日の学習はおざなりになるだろう。
そういっても、だれでも、目の前の誘惑には弱い。だれでも、のどが乾いたら水が飲みたい。お腹がすいたら食べ物がほしい。危ない車が近づいたら逃げたい。だから、楽しいことが目の前にあれば、大切なことを忘れて、飛びついてしまうのは、やむを得ないことかもしれない。
でも、そのとき、君が「こうなっていたい自分」(未来の自分)に気がつけば、誘惑に打ち勝って、君は課題に取りかかるだろうし、学習に取り組むだろう。
課題や学習を前にしたとき、もし「ゲームがしたい。遊びに行きたい。さぼりたい」など、誘惑の感情が起きたら、いちど、自分の感情を止めて、自分を観てみると、いま、やるべきことがはっきりするはずだ。
課題はどうする? 学習はどうする? 自分の問題を意識して、自分に問いかけてみる。すると、自然に答えが見えてくる。
仏教の「止観」という方法であるけれど、僧侶でも感情(煩悩)の制御はむずかしい。したがって、心が目的以外のことに誘惑されそうなときは、ともかく、いちど、感情を止めて、自分を観る。
君たちの場合、ゲーム、スマホ、テレビ、遊びなどに手を出す前に、いちど、その気持ちを抑えて、未来の自分を考えてみよう。いまの自分は、ゲーム、スマホ、テレビ、遊びなどの誘惑に負けそうだとしても、未来の自分は負けない。なぜなら、未来の自分は課題を仕上げることや学習に取り組むことを強く望んでいるからだ。
目的や目標を達成するのは、未来の自分にほかならない。
山手学院 学院長 筒井 保明
取り組んだ人からヒントを得よう!
Take a tip from one who’s tried!

新しい学年がスタートした。まず積極的な態度で、さまざまなことに取り組んでみよう。
そして、見るだけ、聞くだけ、読むだけではなく、自分の口や手や身体を使って、受け入れた情報を声や文字や表現といった形で外に発信してみよう。学習を受動的なものから、能動的なものに変えるのだ。自分の口や手や身体を使うことは、学習の定着度を強化するアクティブ・ラーニングの本質でもある。
学習方法や記憶法に関しては、古今東西、たくさんのことが伝えられてきた。現在では、神経科学の裏づけもあって、生き残った方法もあれば、捨て去られた方法もある。学習習慣のつくり方もはっきりしているし、学習方法より学習環境のほうが重要だという考え方もある。学習方法がわかっていても、誘惑に邪魔されて、そもそも学習できなければ意味がないじゃないか、ということだ。
そもそも学習方法は、学習が苦手な人たちを対象に創出されている。もし、目で見て、耳で聞き、そのまま記憶でき、たちまち理解して、すぐに応用できるなら、その人に学習方法は必要ないだろう。学習において、壁に突き当たったとき、人は、もっと効果的な、もっと効率的な学習方法を求めた。
教育学で有名なマリア・モンテッソーリであっても、独自の指導法で著名なグレン・ドーマンであっても、学習に問題を抱えた子どもたちのために、くりかえし教授法を試行し、やがて効果のある方法を発明した。そして、かれらの取り組みがたくさんの子どもたちの可能性を大きく開いたのだ。
さて、山手学院は、今年で50周年を迎える。振り返ってみると、いつのまにか、イベントやホットラインや小冊子などで、たくさんの教育情報を発信してきた。受験情報など、毎年のように更新される情報もあれば、学習習慣のつくり方など、いつまでも使われる情報もある。重要な情報を得ることで、受験の方向が変化したり、学習法が改まったりする。そして、だれかが取り組んだことによって、その効果がはっきりすると、それをヒントにして、他のだれかが新しい取り組みを始める。
これから、学習環境のつくり方も、学び方も、さらに更新されていくだろう。
山手学院 学院長 筒井 保明
新しい挑戦を始めよう!
Move on to a new challenge!

中学受験、高校受験、大学受験を通して、君たちの挑戦を見ていると、いつも明るい気持ちになる。挑戦する人がいるかぎり、世界に勇気が生まれるからだ。
行きたい学校があって、合格するために学習しよう、と思っている人はたくさんいるだろう。そして、行きたい学校に合格するために学習を始める人もたくさんいるだろう。けれど、行きたい学校に合格できるまで、ねばり強く学習を続ける人は、何人、いるだろうか。
ものごとを成し遂げるために必要なことは、「やろうと思うこと」「やり始めること」「やり続けること」だ。とくに「やり続けること」がもっとも重要であり、もっとも難しい。
今回の受験を振り返ると、合格できる条件を備えていても、当日、緊張してしまって涙をのむ生徒もいたし、合格できる条件をやや欠いていても、当日、潜在する力を発揮して合格を勝ち取った生徒もいた。入試が厳しければ厳しいほど、当日のコンディションが結果を左右してしまう。
ところで、入試の結果により、進学する学校が決まったら、さっぱりと気持ちを切り替えるほうがいい。東京の巣鴨学園の第四代校長の堀内政三先生(1918-2012)は「スウィッチ、スピード、スマート」を標語にしていて、わたしは、『生々主義哲学綱要』(遠藤隆吉著)をいただいたときにお話をうかがったことがあり、「スウィッチ、スピード、スマート」は、わたしのモットーにもなった。
今回、受験を終えた生徒であれば、
進学する学校が決まったら、あたまをスウィッチ!
取り組むことを決めたら、スピード!
そして、進学した学校でスマートに前進しよう!
新しい学年に進む生徒であれば、
新学期に向けて、気持ちをスウィッチ!
目標を決めたら、スピード!
そして、スマートに目標を達成しよう!
「スウィッチ、スピード、スマート」は、なにかを始めるとき、勢いをつけたいとき、集中して上手にやり遂げたいときなどに、ピッタリ合う標語だろう。
今回の受験は、終了した。卒業は、新しい始まりだ。
いま、君は、自分の目的や目標を持っているだろうか。
もし、持っていなかったら、さっそく考えてみよう。
自分の目的や目標を実現しようという気持ちが、学習や行動の原動力になる。君は、自分の目的や目標を意識するたびに、気持が改まり(スウィッチ)、さっそく取りかかり(スピード)、きちんとやり切る(スマート)だろう。そして、学習や行動を続けることができれば、目的や目標が実現するだろう。
さあ、新しい学校や新しい学年で、新しい挑戦を始めよう!
山手学院 学院長 筒井 保明
君のゴール
Your Goal

中学入試、高校入試、大学入試が終わっても、君にとって、それは人生のゴールの通過点でしかない。もちろん、志望校に合格したなら、うれしいだろうし、不合格なら、悔しいだろう。君の取り組みを見ているわたしだって、君とおなじ気持ちを味わうことになる。
うれしくても、悔しくても、進学することになった学校は、君にとって、新しくスタートを切る場所なのだ。ぜひ積極的な態度で、さまざまなことに取り組んでもらいたい。
今回は、大学入学共通テストの現場を見てきたので、小学生・中学生にはずいぶん先のことのようだけれど、すこし状況を説明してみよう。
1 月 13 日(土)の 1 日目は、どの会場も 9 時半にテスト開始。中学受験・高校受験と異なるのは、地理・歴史・公民のうち、2 科目を受験する生徒たちだけが 9 時半開始で、1 科目の生徒たちは 10 時 40 分開始。したがって、朝の開門のときに全員が集合するわけではない。
それでも、試験会場には余裕をもって行くのが鉄則だから、開門時間には多くの生徒たちがやってきた。会場は高校ごとの割り振りであり、試験会場の守衛さんたちや高校の先生たちが待機していて、生徒たちを出迎えていた。おなじ学校の同級生が多いはずなのだけれど、はしゃぐこともなく、みんな緊張の面持ちだ。1 日目は、大学入学共通テストを利用する国立大学と私立大学を志望する生徒たち全員が集まってくるので、受験者数もかなりの人数になる。大学入試センターの発表では、全国で 49 万 1,913 人。
試験会場の待機場所では、早く来た生徒たちが黙々と学習を続けていた。おしゃべりをするような生徒はほとんどいない。わたしは、全員が健闘することを祈った。
1 月 14 日(日)の 2 日目は、理科・数学なので、受験生がグンと減った。守衛さんも一人、二人、高校の先生たちも減り、生徒たちもまばらにやってくる。この試験会場では、国立大学や理数学部を目指す生徒たちが少ないからだろう。そういっても、待機場所での雰囲気は、前日とかわらず、ほとんどの生徒たちが教室への移動時間まで学習を続けていた。
さて、翌週、大学入学共通テストの解答が公表され、受験生たちは自己採点。それと同時に、データネットなどを使って、合格可能性判定基準をチェック。得点や得点率で、A 判定、B 判定、C 判定、D 判定、E 判定に分かれる。わたしは、山手学院高校部の生徒たちの自己採点結果を見た。個々の得点や得点率ではなく、あくまで志望校に対する判定に注目することになる。当然、生徒たち自身、高校の先生方も、志望校に対する判定に注目して、安心したり、不安になったりする。そして、その状況によって、高校でも、山手学院高校部でも、面談が行われる。
山手学院高校部の村元室長の説明によれば、仮に D 判定や E 判定だからといって、その判定がどのくらいの厳しさを表しているのかは、もっと詳細なデータを見なければわからない。さらに 2 次試験を突破できるかどうかは、数字に表れない学力(教えているときの生徒の出来具合やこれまでの成績の分析など)を加味しないと、大学入学共通テストの結果だけでは判断できない、という。事実として、これまでの入試において、A 判定でも不合格者はいるし、D 判定や E 判定でも合格者はいるのだ。大学入試(一般受験)のもっと厳しい勝負はこれからである。
中学 3 年生は、高校入試が終了したら、ぜひ山手学院の高校準備講座を受講してほしい。なぜなら、新高1の一学期から、学校推薦型選抜をはじめとして、実質的に大学入試が始まるからだ。
君のゴールは、まだまだ、ずっと先にある。
山手学院 学院長 筒井 保明
新しい始まり
New Beginning
受験が終わると、つぎは卒業だ。わたしが中学生の頃は、卒業のことを英語で commencement(開始)と教わった。だから、卒業式は、commencement ceremony で、ケンブリッジ英語辞典の定義は「学位授与式」である。
君たちは、卒業のことを英語で graduation と教わるだろう。graduation ceremony は、ケンブリッジの定義では「修了式」である。
英語の commence は「何かを始めること」であり、graduate は「前進すること」「よりよくなること」であるから、けっきょく、卒業も終業も、つぎの新しい始まりにつながっている。ちなみに、卒業は「すべて学業を終えました」ということだから、小学生も中学生も高校生も、それぞれの学校の学習課程を修了したことになる。つまり、一つの段階を終え、つぎの段階に進むのだ。
現在、世の中の変化が目まぐるしいけれど、じつは、君の変化だって目まぐるしい。君の意識の持ち方次第で、昨日の君と、今日の君は、まったく違う君になってしまう。
そもそも自分って、なんだろう?
いま、意識している自分が自分に違いないのだけれど、その自分は過去の記憶でできあがっている。「できる自分」「粘り強い自分」「やる気のある自分」を過去の記憶から引っ張り出して意識しているとき、いまの君は「できる自分」「粘り強い自分」「やる気のある自分」だ。そのままの状態で、なにかに取り組めば、必ず成果が出るだろう。逆に、「できない自分」「投げやりな自分」「やる気のない自分」を過去の記憶から引っ張り出して意識しているとき、いまの君は「できない自分」「投げやりな自分」「やる気のない自分」だ。そのままの状態で、なにかに取り組んでも、なかなか成果が出ないだろう。
ひとは自分が意識している方向に向かうから、「できる」方向に向かえば、できるようになり、「できない」方向に向かうと、できるようにならない。たとえば、自転車を運転しているとき、わき見をすると、わき見の方向に意識をとられてしまうから危ないのだ。もし、わき見を続けたとしたら、思わぬ事故に遭い、目的地に着けないだろう。
君が目標を持っているなら、できるだけ、わき見をしないようにしよう。自分の目標を意識して、いつも目標のほうに向かおう。いつも目標を意識するようにすれば、自然に、目標達成に必要な行動をとるようになる。「いやだな」「めんどうだな」という消極的な気持ちがわいてきたら、ちょっと目をつぶり、自分の目標を思い出して、目を開けたら、即行動を起こす。即行動を起こすことが、消極的な気持ちを打ち消す即効性のある方法だ。
ふりかえってみれば、だれにでも、「できたこと(小さなことでもかまわない)」があるはずだ。その「できた自分」を選べば、君は、できるようになる。
最後に、受験生へのアドバイス
●試験会場に余裕をもって行くこと。●試験会場に自分をなじませて、リラックスすること。●試験が始まったら、目の前の試験に集中すること。● 1 限目の試験が終わったら、それを振り返らずに、つぎの試験に向けて、リラックスすること。● 2 限目の試験に集中すること。(以後、繰り返し)
試験会場の時間も、人生の縮図のようなものかもしれない。一つの終わりは、つぎの始まりなのだ。
入学試験当日は、その日のことに全力で取り組もう。
全力を尽くしたら、笑顔で学校を卒業してほしい。卒業は、新しい始まりなのだから。
山手学院 学院長 筒井 保明