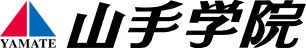目標に向かって、これまでの限界を超えていこう!
You Have No Limits.
 冬期講習のパンフレットの表紙に、「いま、自分に何ができるのか。目標に向かって、これまでの限界を超えていこう!」という標題を掲げた。各期の講習のパンフレットの標題を考えるとき、いつも生徒たちを思い浮かべる。そして、その生徒たちの言動を思い出しながら、「こうあってほしいなあ」というイメージに合わせて、ことばを決める。今回のテーマは、「自分の限界」だ。
冬期講習のパンフレットの表紙に、「いま、自分に何ができるのか。目標に向かって、これまでの限界を超えていこう!」という標題を掲げた。各期の講習のパンフレットの標題を考えるとき、いつも生徒たちを思い浮かべる。そして、その生徒たちの言動を思い出しながら、「こうあってほしいなあ」というイメージに合わせて、ことばを決める。今回のテーマは、「自分の限界」だ。
さて、君の限界は、だれがつくっているのだろうか。
答えをいえば、君の限界は君自身がつくっている。もちろん、君だけではなく、周りの人たちも君の限界をつくっている。「君には無理だよ」とか「もっと現実を見なさい」とか「あきらめたほうがいい」とか、とかく人は自分の思考の範囲内で判断するので、どうしても否定的なことをいう。大人は、君の可能性を制限してしまうことが多い。
でも、君は、未来に向かって成長する存在だ。現状を維持するために生きるわけではない。だから、未来にどんな大きな目標を持ってもいい。自分の目標を達成するために、「いま、自分に何ができるのか」と問いかけて、実行に移すことが必要なのだ。
もちろん、目標は、一つではない。人は、いくつもの目標を持つ。なぜなら、人は内から外に向かって生きる存在であり、自己と他者の関わりのなかでさまざまな目標が生まれるはずだからである。大きな目標もあれば、小さな目標もある。大きな目標は、細分化することができるし、小さな目標は大きく発展させることができる。
たとえば、「薬学者になりたい」という一つの目標があるとする。この目標には、「副作用のない、難病に効果のある薬を発明したい」「病気に苦しむ人を助けたい」のような、もっと大きな目標があるだろうし、逆に、薬学者になるために、「まず大学の薬学部に合格したい」「薬学部に合格実績のある高校に入学したい」「その高校に入るために、現在の成績を改善したい」という小さな目標もあるだろう。さらに、人として、「人類に貢献して、人格を高めたい」「最大限の努力をして、人生を充実させたい」のような抽象的な目標もあるだろう。
ものすごく抽象的にいえば、君自身が目標そのものなのだ。だから、小さな目標であっても、大きな目標であっても、君が目標を達成するために行うことのすべてが、君自身の存在である。
「人は、自分が考えたとおりの人物になる」という格言がある。これは、「君は、君の目標どおりの人物になる」と言い換えてもいいだろう。
なにも考えなければ、君は、いまの時点に停止することになる。
なにか目標を持てば、君は、いまの時点から動くことになる。
限界とは、そこで停止することである。そこで停止しなければ、限界はない。
しっかり自分の目標を考えてみよう。君が本気で達成したいなら、君は、目標に向かって動き出すことができる。
これまでの限界は、たんなる停止線にすぎない。
さあ、目標に向かって、これまでの限界を超えていこう。
学院長 筒井保明
君のエネルギーは無限である。
Your Energy is Limitless.
エネルギーとはなにか。
定義をすると、「働きを成しうる能力」のことである。
エネルギーの分類は、力学的エネルギー、熱、光、化学、電気、原子核などになるが、いずれにせよ、なんらかの形で働く力である。
働きが表れていない状態のエネルギーを位置エネルギーと呼ぶ。学習が手につかず、ぼんやりした状態にあるとしても、じっとしている君は、もしかしたら位置エネルギーを蓄えているのかもしれない。位置エネルギーの例としては、高所に蓄えられたダムの水、強く引かれた弓の弦や輪ゴム、滑り台の上で待機する子どもたち、木の上で蔓を握ったターザン、崖の上に積もった雪…どれも、ある瞬間がきたら、運動エネルギーに変わる。この例は、力学的エネルギーであるけれど、光のエネルギー(放射エネルギー)は緑色の植物を育てるし、化学エネルギーは石油やガスを熱に変え物を動かすし、電気エネルギーや原子核エネルギーは現代文明をつくっているといえるだろう。
もちろん、自然界には、太陽光、風、竜巻、瀧、海流、噴火、温泉、稲妻、地震…
わたしたちの世界は、エネルギーに満ち溢れている。
さて、いうまでもなく、君は、エネルギー、つまり「働きを成しうる能力」を持っている。まさか、ぼくはなにもできないよ、とか、わたしは働けないわ、という人は誰もいないだろう。なぜなら、君は食事をし、食事がエネルギーに変わる以上、働かざるを得ないからだ。「働かざる者、食うべからず」という言い回しがあるけれど、エネルギーの観点からいえば、「食したる者、働かざるを得ず」が正確な表現であろう。
もし、勉強をさぼっている君が、お母さんから「勉強しないなら、ご飯抜きよ」と叱られたとしたら、君は反抗せずに黙って机に向かい、お腹が鳴ったタイミングで、「お母さん、お腹がペコペコだ。エネルギーを補給しないと、これ以上、勉強できない。だから、ご飯にしてよ」といえばよい。大人は、筋が通っていれば、必ずわかってくれるものだ。エネルギー源のないところから、エネルギーは生まれない。
食事を終えた君は、「食したる者、働かざるを得ず」で、ふたたび、机に向かうことになる。ただし、食べ過ぎていると、血液は胃腸に向かっているので、頭がよく働かない。だから、学習者は、食べ過ぎてはいけないのだ。
明治・大正時代の学習の秘訣に、
① 食を細くする。(頭が回らないから) ※現代であれば、消化の良いものを食べる。
② 新聞を読まない。(記憶力が衰えるから) ※現代であれば、テレビを見ない。
③ 教科書をくりかえし読んで寝てしまう。(よく記憶できるから) ※神経科学として正しい。
というのがある。とても理にかなった方法で、テスト勉強、受験勉強にピッタリだ。
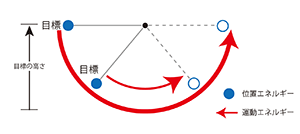 最後に、君のエネルギーを最大限に引き出す方法を教えよう。
最後に、君のエネルギーを最大限に引き出す方法を教えよう。
目標をできるだけ高くすること!
受験でも、スポーツでも、芸術でも、習い事でも、同じだ。目標を高くすることは、位置エネルギーを大きくすることにつながる。高い目標であればあるほど、君の位置エネルギーが増える。そして、君が本気になれば、その位置エネルギーが運動エネルギーに変わるのだ。
学院長 筒井保明
学習速度を上げる
Speed Learning
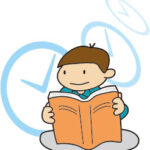 誰にでも時間は平等に与えられている、という人がいる。誰でも一日の持ち時間は24 時間ということが根拠だろうけれど、本当だろうか?
誰にでも時間は平等に与えられている、という人がいる。誰でも一日の持ち時間は24 時間ということが根拠だろうけれど、本当だろうか?
二人の人を並べて、静止した状態で時間を計るならば、なるほど同じ24 時間である。
しかし、人は動く。動く速度も、考える速度も、仕事をする速度も、勉強をする速度も、人によって大きく異なる。地球上を経過する物理的な時間は同じであっても、私たち一人一人が持っている時間は、実質的にずいぶん違うのではなかろうか。
一人の観察者から見て、静止した人の持つ時間ととても速く動く人の持つ時間は、特殊相対性理論では、 によって異なる。t′は、ある速度を持って動く人の時間、t は静止状態の時間、v は動く人の速度、c は光速で秒速30 万キロメートル。変数はv である。静止した人の速度は0であるから、1時間(3600 秒)はそのまま1時間である。もし君が光速の半分の秒速15 万キロメートルで動くとしたら、ある観察者から見て、君の時計は、1時間ではなく、52 分を指している。光速の10 分の9で動くとしたら、君の時計は26 分を指している。つまり、速く動けば動くほど、時間が縮むのだ。
によって異なる。t′は、ある速度を持って動く人の時間、t は静止状態の時間、v は動く人の速度、c は光速で秒速30 万キロメートル。変数はv である。静止した人の速度は0であるから、1時間(3600 秒)はそのまま1時間である。もし君が光速の半分の秒速15 万キロメートルで動くとしたら、ある観察者から見て、君の時計は、1時間ではなく、52 分を指している。光速の10 分の9で動くとしたら、君の時計は26 分を指している。つまり、速く動けば動くほど、時間が縮むのだ。
もちろん、地球上で生活する以上、光速に近づいて動くことなどないので、身体的な時間は変わらない。しかし、頭(脳)の中の時間はどうだろうか? 直感や閃きは、膨大な情報を瞬時に処理した結果だから、ものすごい速度で頭が働いたはずだ。学習は、声や手を使うけれども、本質的には脳の情報処理である。だから、速度を上げることはできる。学習は、「習うより慣れよ」で、慣れれば慣れるほど、速くなることを君も実感したことがあるだろう。(計算練習による速算や読み取り練習による速読など)学習速度が速くなれば、脳のなかの時間は縮む。つまり、同じ1 時間でも、断然、学習量が多くなるのだ。
では、実際に、学習速度を上げるためのトレーニングをしてみよう。今回は、社会科の教科書を使う。
- リラックスして、教科書を読む。(一冊丸ごとでもいいし、各章ごとでもいい)読み終わったら、読み終わるまでにかかった時間を記録する。
- もう一度、教科書を読む。(当日でもいいし、別の日でもよい)今回は、意識して速く読む。読み終わったら、かかった時間を記録する。
- もう一度、教科書を読む。意識して速く読む。時間を記録する。(この3 回目で、すでに最初より速く読めるようになっているはずだ)
- もう一度、教科書を読む。意識して、できるだけ速く読む。時間を記録する。(読後に、問題集に取り組んでおくと、さらに効果的だ)これを何日かかけて、10 回以上繰り返す。
10 回目を超えるころには、最初と比べものにならないくらい速く読めるようになっている。
まず繰り返して文章を読んでいると、文字の認識力が高まるので、読む速度が速くなる。また、社会科の用語が定着してくるので、知らない用語で止まることが減り、読む速度が速くなる。また、部分によっては記憶してしまうので、先の予測ができ、さらに速くなる。定着した知識が増えれば増えるほど、速度に拍車がかかる。一字一句とばさずに速く読めるということは、書かれている内容を自分のものにしていることの証拠でもある。(問題集を解いてみよう!)
専門家が専門分野の書籍をものすごい速度で読むことができるのは、定着している知識が多いからである。その分野、その教科が得意になればなるほど、学習速度は速くなる。
いちど速く学ぶことを体得してしまうと、どの教科にも応用が利く。ぜひ実行してほしい。
学院長 筒井保明
世界の視点で
Global Studies

国に先駆けて、さいたま市では、すべての市立小中学校で、新しい英語教育「グローバル・スタディ」が実施されている。教育目標は、「将来、グローバル社会で主体的に行動し、たくましく豊かに生きる児童生徒の育成」。さらに、目指す子ども像として、「外国の方と英語で積極的にコミュニケーションを図ることができる子ども」「日本やさいたま市の伝統・文化に誇りをもち、将来にわたり、社会に貢献する子ども」を掲げている。<br />
これからの日本や世界の状況を予想したとき、グローバル・スタディという取り組みの方向性は、正しい。取り組みの効果に疑問を持つ方々も多いようだが、グローバル社会に英語は不可欠になるので、失敗の可能性を論じてもあまり意義はないだろう。もし高い学習効果を期待するならば、いちばん簡単な方法は、子どもたちの目の前にグローバルな状況を出来させてしまうことだ。<br />
現在、山手学院のジュニア英語では、さまざまな国の、英語を国際語として使っている学生たちを授業アシスタントとして起用し始めている。これは、さいたま市の意図と同じく、彼らを教室に入れることによって、子どもたちの意識を日本語の世界からグローバルな世界に移動させ、体感として英語を学んでもらうためである。<br />
じっさい、外国の学生たちが入ったジュニア英語の授業を眺めていると、子どもたちは無意識のうちに彼らに英語を使おうとしている。なぜなら、目の前の人物が日本人でなく、どうやら英語を話せるらしいと認識すると、子どもたちの言語モードが日本語から英語に変わってしまうからだ。この状態で英語を学習すると、それが片言であっても、使える英語として身についていく。「英語が使える」という実感こそ、英語学習の鍵である。<br />
英語は、4技能習得の時代に入った。「聞く」「話す」「読む」「書く」をバランスよく身につけることを学習目標としているわけだが、言語習得の自然として、①「聞く」②「話す」③「読む」④「書く」という順番で、英語力をつくっていくべきだろう。<br />
わたしたちが日本語を身につけた順番も、①「たくさんの言葉のかたまりを聞いた」(Listening)②「聞いた言葉を自分の口でくりかえし話した」(Speaking)③「文字を読めるようにして、たくさん音読した」(Reading)④「くりかえし文章を書く練習をした」(Writing)である。<br />
小学生も、中学生も、積極的な気持ちで、英語を学べば、必ず英語は得意になる。これまでは英語を使う環境がそもそもなかったが、これからはグローバルな環境が身近なものになってくる。英語が必要な機会が増えてくる。<br />
いままで日本人が英語を苦手としていたのは、実感のない知識としての英語だったからだ。今後、君たちは、体感をともなって英語を学習することができる。日本自体が、そういう環境に変わってくる。<br />
さあ、いよいよ夏休みであるが、君たちは、世界の視点を持つために、なにをしたらいいのだろうか。<br />
まず目の前にある学習にとことん取り組んでみることを勧める。<br />
夏期講習・夏期合宿・サマースクールも、重要な学習機会になる。<br />
長い夏休みを無為に過ごすことなく、ともかく、たくさんのことを学んでいこう。<br />
できるかぎり学び、そして果敢に行動することによって、君たちは世界の視点を持つことができるようになる。<br />
体験が君の未来を変える!
Experience makes the difference!
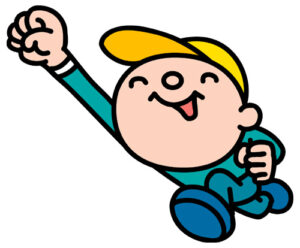 時と所が変われば、物の見方が変わる。
時と所が変われば、物の見方が変わる。
私たちは、日本の教育について、どちらかというと否定的な意見を述べがちであるが、日本にいる外国人は、日本の基礎教育の充実をほめてくれる。「読み・書き・そろばん(計算)」の底力が、日本を支えているという見方である。
ところが、先日、日本の大学の工学研究科博士課程で学ぶネパール人と話したとき、基礎教育と対極にあるはずの、日本の大学院の問題点を指摘された。彼の交流範囲の修士・博士課程で学ぶ留学生たちは、「日本の大学院は、徒弟制度のようだ」といって、批判するそうだ。つまり、指導教授が親方で、親方の守備範囲(研究テーマ)から徒弟(学生)は外れることができず、研究内容や研究手段も指定され、新しいテーマに取り組むことができない、というのだ。
彼は、大手建設会社から奨学金をもらい、国際的な研究発表会にも出席する優秀な学生であるが、彼が現在の大学院を選んだ理由は、「教授」であった。研究テーマを自分で決めることができ、研究手段に助力してもらえるからだという。
彼は、ほとんど日本語ができない状態で、日本に来た。英語はネイティブ並みにできるが、日本語は手探りだった。博士課程で研究するほどの日本語力を彼はどこで身につけたのだろうか?
日本語学校にも行ったけれども、彼の実感としては、彼に親切にしてくれた人たち(アルバイト先や近所の方々)とのたくさんのコミュニケーションのおかげであった。
「ともかく、人の中に入っていきました。たくさん話しかけて、何度も日本語を直してもらいました。ものごとを身につけるためには、積極性が必要です。日本の学生は、引っ込み思案のせいで、とても損をしています。各国で開催される研究発表会にも、英語が不安だといって応募しない。研究者の集まりに入ろうとしないから、もっと勉強しようという感じになりません」
わたしは、彼が日本に来たころの状況を聞いて知っているから、
「君は、とことん前向きだなあ。一時、住むところもなかったようにはとても見えない」
「努力や苦労はしておかなければだめです。後で考えると、全部、自分の役に立っています。たとえば、外国免許証の切り替えは、テストは簡単ですが、運転技能は難しい。でも、合格するまでに何度も直されたことが、あとで役立ちます。たしかに事故が防げます。体験しておくと、本当に動き方が変わります」
この後も、彼は、体験の重要性をくりかえし語った。
体験という同じ観点でいえば、山手学院では、夏期勉強合宿(中3・中2・小6受験・小5受験)、個別スクール合宿(中3)、サマースクール(小3~小6)を実施し、いずれも重要な体験の機会になる。夏期勉強合宿や個別スクール合宿では、日常から離れて、長時間、集中して学習することによって、集団的効力感のなかで自分の潜在能力(やればできる)をしっかり実感できる。そして、効果的、効率的な学習の仕方を身につけることができる。サマースクールでは、自然体験、グループ体験、国際交流によって、自分の世界をグンと広げることができる。さまざまな出会いは、小学生にとって、大量の体験学習になる。
小学生・中学生時代の体験は、君の未来をつくる。ことわざに「馬には乗ってみよ、人には添うてみよ」という。引っ込み思案にならずに、なにごとにも積極的に取り組もう。
学院長 筒井保明
いま、君は、目標に向かって、進んでいる。
You’re on your way to achieve your goal.
男子4人、それぞれの前学年の通知表評定が、全員、9科目合計で30であった、とする。
それぞれの反応が、A君「まずい!」、B君「まずい!」、C君「まずい!」、D君「別に」であった。このとき、A君とB君とC君は、同じように見える。D君は、関心がない? じつは 全員、通知表評定という出来事に対する受けとめ方が違った。
A君は、日ごろから「父母をよろこばせたい」という考えであるから、「父母をよろこばせることができない」と受けとめて、「まずい!」と反応した。
B君は、志望校の推薦入試の条件が評定合計37であるから、「志望校に推薦してもらえない」と受けとめて、「まずい!」と反応した。
C君は、いつも同級生にいろいろと言われるから、「バカにされるかもしれない。はずかしい」と受けとめて、「まずい!」と反応した。
D君は、通知表がよかったらゲームを買ってもらえる約束をしていたが、それほど欲しくなかったので、「ゲームを買ってもらえないけど、どうでもいいや」と受けとめて、「別に」と反応したのである。
さて、先生は、この4人に対して、どういう面談を行ったらいいのだろうか。
成績に関しては、生徒の目標が設定されていないと、論理的に話すことが難しい。評定合計30が、いいのか、わるいのか。目標がなければ、判定できない。
B君の面談は、かんたんである。「推薦入試のためには、通知表を37以上にする必要がある。本気で目指すなら、中3の1学期の通知表を上げることだ。具体的な取り組みは…」と取り組み方法を指示して、励ませばよい。
A君の面談は、ちょっと回り道になるが、「ご父母の希望は、具体的にどれくらいだ?」「36以上です」「君は、本気でご父母をよろこばせたいのか?」「はい」とうなずいたならば、「では、具体的な取り組みは…」と取り組み方法を指示して、励ませばよい。
C君は、受けとめ方による悩みであるから、論理的に「他人が君の成績を批判することはできない。君がはずかしいと思うだけで、同級生は君の成績にまったく関係ない」ということを納得させて、「君の目標は?」「○○です」「それを達成する具体的な取り組みは…」と取り組み方法を指示して、励ませばよい。
いちばん問題なのは、D君である。ご褒美を目当てとした努力は、ご褒美が必要でなくなったとき、動機を失ってしまう。たとえば、お母さんをよろこばせるためにお手伝いをしている子どもは、いつでもお手伝いができるけれど、お小遣いが目当てでお手伝いをしている子どもは、お小遣いがもらえないとき、手伝う気持ちを失いがちだ。
D君に対しては、学習はご褒美のためにするものではなく、自分の目標を実現するためのものであることをしっかり認識させなければならない。そうしないと、「なにも買ってもらえないなら、なにもやらない」という反応が生じる恐れがある。学習の主体は、自分だ。「目標に対して、通知表の評定は○○以上が望ましい」という考えをもっていれば、通知表を分析することによって、これからやることが決まってくる。D君に必要なものは、自分の目標(達成したい数字)と、「やればできる」という確信である。
自分の目標と「やればできる」という確信があれば、どんな結果も、目標を達成しつつある自分の励みになる。
いま、君は、目標に向かって、進んでいる。
学院長 筒井保明
将来の自分を生き生きと思い描こう!
Self-image determines your life.
人は、目標に向かって成長する。目標があるから、やりたいこと・やるべきことがはっきりわかる。目標は、モチベーションを生み出すことができる。
では、目標とは、なんだろうか?
抽象化して言えば、目標とは、「このようでありたい自分」「このようでありたい世界」ということだろう。だから、「わたしは、こうありたい」「わたしの世界は、こうありたい」と思うことは、すべて自分の目標になる。学業であっても、スポーツであっても、芸術であっても、受験であっても、仕事であっても、君が本気で望むことは、すべて目標になる。
病んでいる人を救っている自分。困っている人に助言している自分。英語で世界中の人と交流している自分。スポーツの世界で抜群の能力を発揮している自分。米国に留学して経営学を学んでいる自分。志望校に合格している自分。定期テストで満点を取っている自分。お手伝いをしてお母さんに喜ばれている自分。…
遠い未来から、近い将来まで、目標はいくつあってもかまわないし、どんな自分でもかまわない。なぜなら、現状に制限されることなく、君が信じるかぎり、どんな目標も達成可能だからである。
さて、目標達成のためには、肯定的な自己イメージをつくることが必要だ。なぜなら、自己イメージを実現するように人は自分を仕上げていくからである。
たとえば、A「学習が得意な自分」とB「学習が苦手な自分」がいると仮定する。
君は、AとBをそれぞれ生き生きとイメージしてみる。Aであれば、余裕の笑顔で問題を解いている自分の姿を、鉛筆の音やうれしい気持ちなどを含めて思い描く。Bであれば、ゆがんだ顔で真っ白な答案用紙の前で固まっている自分の姿を、苦しみや冷や汗などを含めて思い描く。(AとBを同時にイメージすることはできない)
Aをしっかり思い浮かべた後、ためしに「わたしはAではない」と言葉で否定してみよう。否定してみても、君の頭に残るイメージは、「学習が得意な自分」のままだろう。
Bをしっかり思い浮かべた後、こんどは「わたしはBではない」と言葉で否定してみよう。否定してみても、頭に残るのは「学習が苦手な自分」のイメージで、学習が得意な自分は浮かんでこない。
これが、イメージの力で、イメージは、言葉よりもはるかに強い。だから、「学習が得意な自分」をイメージしてから、それを打ち消すために「学習が得意な自分ではない」と言葉で否定しても、君の中のイメージは「学習が得意な自分」のままである。
少しややこしくなったけれど、これは重要なことだ。
一流のスポーツ選手は、必ず最高の選手である自分をしっかりイメージする。失敗や失策をしている自分ではなく、成功やファインプレーをしている自分を自己イメージとして持っている。だからこそ、一流のスポーツ選手になっているのだ。
同じように、君が「学習が得意な自分」をしっかり思い描いているなら、否定的な意見など、跳ね返してしまうことができる。そして、自己イメージを実現するために、君は、知らず知らずのうちに学習に取り組んでしまう。
未来の自分を意識して、ぜひ肯定的な自己イメージを思い描いてほしい。
学院長 筒井保明
新しい感動と新しい響きのなかへ出発しよう!
Depart in new affection and new sound!
日本の教育の世界で、アクティブ・ラーニングという言葉が頻繁に使われるようになっている。
教育に関して、日本はいつも後追いであり、1991年の※「アクティブ・ラーニング(クラスルームに感動を作り出す)」というレポートあたりが引き金になっているのだろう。
学習効果が、学習者の能動性・受動性に左右されることは、ずいぶん昔から指摘されていることだ。
最初の問いかけは、「受動的な方法で、人は、学ぶことができるのだろうか?」であった。
受動的な方法とは、授業形式のことである。授業を聞く生徒を調べた結果、平均値として、授業開始10分から15分のあいだに集中力は最高になるが、その後、徐々に下がっていくことがわかった。もちろん、教師の工夫で、集中力を取り戻すこともできるのだが、全体としては下がっていく。そして、集中力の持続時間は、生徒の学力に基づくこともわかった。学力が低い生徒は短く、学力が高い生徒は長い。つまり、学力の高い生徒にとって授業形式は有効であるが、学力の低い生徒にとって授業形式は効果が低い。
学校がアクティブ・ラーニングを進めていくとしても、さしあたっての問題は、「生徒の学力層を分けることができるのか」ということになる。そして、「能動的な学習への移行は同時にリスクが高くなるという事実に対処できるのか」ということになる。(この二つの問題を解決しないと、アクティブ・ラーニングはうまくいかない)
さらに、教師の力量も問題になる。学力層に合わせた適切な問いかけができなければ、議論や討論をともなうアクティブな授業は成立しない。また、入学試験を経た後の高校や大学ならば学力層が均質であるかもしれないが、公立小学校・中学校では学力差が大きい。
そういっても、この議論は、教師側から見たアクティブ・ラーニングであり、君たちは、生徒側からアクティブ・ラーニングをとらえればよい。
まず受動的学習(パッシブ・ラーニング)とはなにか。「読むだけ。聞くだけ。見るだけ。見て、聞くだけ」ということだ。つぎに能動的学習(アクティブ・ラーニング)とはなにか。「話す。書く。行う。教える」ということだ。
ある統計では、学習の定着度を「読むだけ10%。聞くだけ20%。見て、聞くだけ50%。話して、書く70%。やってみる90%」としている。あるいは、「読む10%。見て、聞く20%。実演を見る30%。話し合う50%。やってみて繰り返す75%。人に教える90%」となっている。
私自身は、正直、「ほんとうか?」と思う。「どういう読み方をしたか」「どういう聞き方をしたか」「見て、聞いた後、なにをしたか」を問題にしないと、土台のない学習になるリスクがある。
「受動的学習は、入力。能動的学習は、出力」ととらえれば、どちらも重要であることがわかる。
おもしろいことにアクティブ・ラーニングのレポートを読んでいると、君たちではなく、先生の方がよく学べることになる。なぜなら、人に教えることが最も学習効果が高いからだ。
君たちにとってのアクティブ・ラーニングとは、「話すこと・書くこと・試してみること・人に教えること」にほかならない。「読むこと・聞くこと」は、そのための土台である。土台となる知識や能力があってこそ、積極的に、自主的に学ぶことができる。
しっかり授業を受けることからスタートしよう。
※Active Learning : Creating Excitement in the Classroom by Bonwell and Eison
学院長 筒井保明
新しい感動と新しい響きのなかへ出発しよう!
Depart in new affection and new sound!
「もう眺めるのに飽きてしまった。もう十分だ。もう知りたくもない。どの音もどの眺めも、 人生の停滞だ。さあ、新しい感動と新しい響きのなかへ出発しよう!」 そういって、フランス生まれのアルチュール・ランボーという 17 歳の詩人は、イギリスの首都ロンドンから旅立った。
学年の変わり目で、君たちも、「現在の学年でやるだけやった。もう十分だ。さあ、新しい学年に出発しよう!」と、決意を新たにしているかもしれない。どの学年であっても、その学年の学習を十分に学んでいると、その学習に飽き足りなくなってくる。次の学年 に進むことが待ちきれない。もっと新しいことが学びたい。もっと発展した学習に挑みたい。もっと、もっと、できるようになりたい。
君たちのそういう気持ちが、次の学年を充実させていく原動力になる。だから、ぜひ、いまのうちに、その気持ちをくりかえし確認しておこう。一方、「私は不安だ」「僕は心配だ」という人もいるだろう。その気持ちこそ、君たちにとって最大の邪魔物で ある。君たちの不安や心配は、言い換えれば、「取り越し苦労」であり、「杞憂」である。取り越し苦労や杞憂は、君たちの人生を損なう危険性をもっている。
『列子』に、「杞の国に、天地が崩れ落ちることを憂うる人がいた。身を寄せるところがなく、寝食を忘れてしまった。それを心配した人が、〈天は気が満ちているところで、君はそこで呼吸しているのだから、空は崩れ落ちないよ〉 と諭した。憂える人が、〈じゃあ、太陽や月や星々も落ちないのか〉と聞いた。諭す人は、〈それらも気のなかで 輝いている。落ちたとしても、君には当たらないよ〉と答えた。〈じゃあ、地面が崩れたら、どうするんだ〉〈地 は塊が満ちているところで、空間を埋めている。足を踏みつけて歩いてみろよ。心配なんかあるものか〉憂える人が納得して大いに喜んだので、諭した人も大いに喜んだ」とあるのが、杞憂の故事である。
学習に関して、「私は不安だ」「僕は心配だ」というのは、杞憂だ。 そもそも学習に取り組んでいないのは論外であるけれど、君たちが「できるようになりたい」という気持ちで 学習に取り組み、その学習方法にまちがいがなければ、必ずできるようになる。そして、君たちの学力は、確実に上がっていく。
ところが、取り越し苦労や杞憂で、君たちが不安や心配を感じているとき、君たちは緊張状態にある。緊張状 態は、学習をする状態ではないから、気持ちが焦るばかりで、学習効果が低い。 「学習に、不安や心配はない。わからないも、できないも、取り越し苦労に過ぎない。私は必ずできる」と考えて、 ゆっくりと呼吸しながら肩の力を抜いていく。リラックス状態が学習を始める前に必要だ。 学習中、やってはいけないことは「ながら勉強」。(新しい記憶の形成を妨げる) 学習のコツは、「まちがえた問題は必ず正答を確認すること」「できなかった問題は正解するまでくりかえすこ と」である。たったこれだけでも、学習効果がグンと高くなる。 さあ、新しい学年で楽しく学んでいこう。
学院長 筒井保明
確信を持って自分の目標を持とう
Hold on to your purpose affirmatively!
なぜ、君は学習から逃げてしまうのか?
なぜ、君は学習が苦手なのか?
学習は、本来、進んで取り組みたくなるものであり、誰でも得意になることができるものであるのに、
なぜ、君は学習から逃げ出し、自分から苦手になってしまうのか?
学習に直面したとたん、暗い気分に落ち込んで、学習しない理由ばかりを探していたのでは、まったく前に進めない。
学習の根幹は、「学びたい」という気持ちである。「学びたい」から、進んで学習に取り組むことができる。そ
して、「学びたい」気持ちは、いつも積極的なものであるから、学習効果がきわめて高い。学習方法が正しければ、
必ず学習は得意になる。
ところが、教科書やテキストを手にしたとき、顔色が曇る生徒たちがいる。どうやら脳の扁桃体がアラームに
なって、嫌な気持ちを引き出してしまっているようだ。
どういうことかというと、たとえば、過去に、学習に関して、誰かから酷く叱られた経験があると、
そのとき「嫌だ!」と思った記憶が、言語的に(論理的に)処理されないまま、
学習=「嫌だ!」という状態で脳に刻みつけられてしまう。
これがトラウマと呼ばれる心の傷で、ふだんは意識されていないのに、教科書やテキストを手にすると、
学習=「嫌だ!」と扁桃体がアラームを発する。そして、嫌な気持ちになっているあいだ、学習をつかさどる脳の海馬という部分の働きが急速に鈍る。「嫌だ!」という気持ちの生徒は学習できない。
(始末が悪いことに、この「嫌だ!」は非言語であるから、どうして嫌なのか、その生徒は説明することができない)
もし、酷く叱られたとき、「これは僕が悪かった。お母さんはテスト結果を楽しみしていたのだから、きちん
と学習して、お母さんを喜ばせるべきだった。お母さんは、僕の将来のことを真剣に考えてくれている。今回のことを反省して、次回はしっかり学習しよう」と、目の前の事態を論理的に処理していたなら、学習を嫌うようにはならない。
じつは、学習自体に関しては、絶対に叱るべきではない。「どうしてできないんだ!」と怒鳴って、怖い顔で
睨みつけることは、ただ子どもを学習嫌いにするだけである。その子どもは、学習やテストのたびに、その怖い
顔を呼び起こし、「嫌だ!」という気持ちを強めてしまう。(残念ながら、君が叱られている場合、相手が叱る理
由を考えるのだ。そうすれば、学習自体を嫌になることはない)
誰でも、学習はできるし、必ず得意になることができる。自分自身の目標を持つことができれば、学習の方向
も心の置き所もしっかり定まる。学習から逃げない方法も、学習を苦手にしない方法も、かんたんにいえば、同じである。
「確信をもって自分の目標を持つこと」
何度も考えて、「これが私の目標だ」というものを持つことができれば、学習から逃げることも、苦手になることもない。
本当に行きたいと思っている学校に合格するためには、学習は、「取り組まなければならない」ことではなく、
どうしても「取り組みたい」ことになる。
2016 年が、君にとって、大きな成長の一年になることを願っている。
学院長 筒井保明