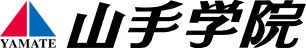ともに成長する。
We all grow together.
「ご縁」という言葉がある。お釈迦様なら、君が、いま、ここに存在すること自体が「ご縁」であるというだろう。
世界(あるいは宇宙)の森羅万象の結び目の一つが「自分」であるから、たしかに私も君もご縁(結び)によって、いま、ここにいる。「共生」(きょうせい・ともいき)という考えも、生きとし生けるものがすべてご縁で結ばれていることを踏まえて、みんなでともにつながって生きていこう、と呼びかけているのだ。
ところで、君たちは、「さあ、勉強しようぜ」とか「いまから数学をやりましょう」とか、友だちに呼びかけているだろうか。
もし、そういった呼びかけをしていないなら、これからは、そうしよう。テストが近づいてきたら、「もうすぐ定期テストだ。テレビを見るのをがまんして、しっかりテスト範囲を勉強しようぜ」とか「北辰会場テストが 2 週間後ね。さあ、準備を始めましょう」と、君から友だちに声をかけるようにする。すると、君に不思議なことが起きる。
そう友だちに呼びかけることによって、君にやる気が起きるし、学習効果も格段に上がる。
もっといいのは、呼びかけるだけではなく、苦手な教科をもつ友だちに教えてあげることだ。教えることによって、君は、もっとできるようになる。
コセコセと自分の得ばかり考えるような人は、結局、得はしない。相手のためを思って、善意の働きかけをしていると、自分も成長する。かりに君がゲームばかりしていてテストの準備を怠っているとする。そして、悪心が兆きざして、君は、勉強している友だちに「いっしょにゲームしようぜ」と誘いかける。君に誘われた友だちは、誘惑に負けて、学習をやめてしまう。このとき、君は、友だちにとって悪魔になっている。
いっぽう、君は一生懸命に勉強している。君の友だちはアニメばかり見て、勉強をさぼっている。君は、友だちに「友よ。いっしょに勉強しよう。君はやればできるのだから」といって、学習を呼びかける。友だちもその気になって、勉強を始める。こちらの君は、天使になる。君が勉強し、友だちが勉強し、さらにその友だちが勉強し、いつのまにか、クラス全体、学校全体が勉強するようになったら、なんとすばらしいことであろう。
ポール・マッカートニーの歌に、We All Stand Together という蛙(かえる)の歌がある。
Win or lose, sink or swim /
One thing is certain we’ll never give in / Side by side, hand in hand / We all stand together (勝っても負け
ても、沈んでも泳いでも/一つ確かなのは、僕らはけっしてあきらめないってこと/並んで、手に手をとって/
僕らみんなともに立っている)
蛙たちでさえ、みんなともに立っているのだから、君たちはともに立つだけではなく、ともに成長しようでは
ないか。
ともに学び、ともに成長することは、小学生でも、中学生でも、そして、いくつになっても、とても重要なこ
とだろう。「ご縁を大切にする」とは、君たちが、周りのみんなと、ともに成長することである。
さあ、みんなでいっしょに学んでいこう。
学院長 筒井保明
よく考えることに努めよう!
Let us endeavor to think well.
人は考える葦である、というパスカルの言葉を、君たちも聞いたことがあるだろう。パスカルの『パンセ』という断片集には編集の異なるものがあるけれど、最初の編集では、346、347、348と続く部分が、「考える葦」に当たる。
346「思考が人の威厳をつくる。」
347「人は葦に過ぎない。自然の中で最も弱いものだ。しかし、それは考える葦である。人を押し潰すのに宇宙全体が武装する必要はない。人を殺すには、一滴の水蒸気、一滴の水で十分である。しかし、宇宙が人を押し潰すとしても、人は人を殺すものよりもはるかに高貴であろう。なぜなら、人は死ぬことも、人に対する宇宙の優位性も知っているが、宇宙はそれについて何も知らないからだ。したがって、私たちの尊厳は、思考に存する。そこにこそ、私たちは立ち上がるべきであって、私たちが満たすことができない空間や時間の中ではない。したがって、よく考えることに努めよう。これが倫理の原則である。」
348「考える葦。私が尊厳を探すべきところは、空間ではなく、思考の枠組みの中である。土地を所有しても、勝るわけではない。空間によって、宇宙は私をとりまき、一つの点のように私を取得する。思考によって、私は宇宙を理解する。」
長々と訳したのは、「本当の理解は、全体から来る」ということを知ってほしいからである。名言集というものがたくさん出版されているけれども、一行や二行、取り出しただけでは、本当のところはわからない。(文学でいえば、あらすじでは、名作を味わうことはできない)パスカルがいいたいことは、「人は、物理空間のなかでは、一本の葦のように弱いものでしかない。しかし、人は思考によって情報空間をつくることができ、真実を知る努力によって、宇宙さえも理解していくだろう。真実を知る努力、つまり、思考こそが人の尊厳なのだ」ということではないだろうか。
「人は考える葦である」という言葉は、「よく考えることに努めよう」という言葉とセットになっている。そして、「よく考えることに努めることが倫理の原則である」という言葉は、「思考が人の威厳をつくる」ということなのだ。『パンセ』の最初の編集者が、346、347、348と並べたのは、以上のように考えたからであろう。パスカルの言葉の素晴らしいところは、「よく考えろ」と突き放して命令するのではなく、「よく考えることに努めよう」(Travaillons à bien penser)と励ましてくれるところだ。日本には「下手の考え休むに似たり」ということわざがあるけれど、パスカルなら、「下手は下手なりに、一所懸命に考えることが、人の尊厳をつくるのだ」といってくれるだろう。
わたしは、パスカルに賛成だ。パスカルは、「考えて結論を出せ」といっているのではなく、「命ある限り、真実を知るために、よく考えることに努めよ」といっているのだ。たとえば、パスカルの時代、17世紀の人たちは、相対性理論もビックバンも知らない。21世紀の現在、さらに多くのことが発見され、わかるようになっていくだろう。しかし、際限はない。宇宙と対面していたパスカルは、宇宙に際限がないことを知っていた。だから、自然の中で、ひとつの葦のように弱い私たちは、よく考えることによってのみ、自分の存在を支えることができる。
「よく考えることに努めよう!」という言葉は、すべての人に対する励ましの言葉である。
学院長 筒井保明
学ぶことは、生きることだ。
Learning Is Living.
グローバル化経済が、確実に進んでいる。外国人雇用の届け出だけを数えても、1994年の13万人から2014年の79万人に増加している。在留外国人の数だけであれば、2014年12月の時点で、212万人、埼玉県に限ると、13万人の外国の人たちがいる。
パナソニック、東芝、ソニー、ユニクロ、野村証券など、多くの上場企業が外国人採用に積極的だ。君たちが社会に出る頃には、上司や先輩が外国人である可能性も大きい。
2015年の中国の大学卒業者は、749万人、日本の大学卒業者は、42万人。人の脳に人種による優劣はないので、かりに中国の大学生と日本の大学生が同等に学習したとすれば、中国人のトップ6.7%(偏差値65以上)だけで50万人を超えるのだから、日本人としては背筋が寒くならないだろうか?
さらにいえば、中国人の大学生は、日本人の大学生と比べて、猛烈に学んでいる。
日本の大学に通うネパール人やスリランカ人やベトナム人や韓国人やアメリカ人の大学生・大学院生に話を聞くと、異口同音に「日本人の大学生・大学院生は、例外はあるけれど、ほとんど勉強しない」と断言する。つまり、10年後、20年後、君たちの日本は、かなり衰退している恐れがあるのだ。
では、その引き金は何であろうか?
おそらく環太平洋パートナーシップ(TPP)の締結であろう。TPPが、物流だけではなく、人の流動性を大きく促進する。外国の人たちが、君たちの競争相手として、すぐ目の前にいることになる。
さあ、この状況を前向きに捉えるか、後ろ向きに捉えるかは、その人の実力や価値観によって異なるだろう。いずれにせよ、「英語は嫌いです」「外国人は苦手です」では、勝負にならないのだ。
英語は、国際語としての地位を確立している。多くの国において、ビジネスの現場では母国語よりも英語である。また、外国人に苦手意識を持つのは、単に慣れていないからで、本質的なところで、どの国の人も「人情」は同じである。
英語に限らず、すべての言語は、生きた場面で使うことによって、はじめて自分が使える言語になる。経験するとわかることだが、日本語が通じない環境において、自分の意思を伝えようと思うとき、自分の脳に日本語は浮かんでこない。得意でない外国語であっても、脳に浮かぶのは片言の外国語である。
君たちの英語学習は、身につける学習 Learning である。学ぶことは、生きること Learning is Livingである。すべての学習は、生きることにつながっていることに気がつけば、英語など、恐れることはない。生きている人間の使っている言葉は、君がその言葉を使うことによって必ず身につけることができる。たとえば、アメリカ人に向かって、“Good morning.”、中国人に向かって、“早上好。”(ツァオシャンハオ)、ロシア人に向かって、“Доброе утро.”(ドーブラエ ウートラ)と呼びかけたことがなければ、朝の挨拶もうまくいかない。しかし、一度、挨拶を交わせば、その言葉は完全に君のものだ。
いま、英語教育が変わろうとしているけれども、使える言葉を身につけることを意図している。音声として英語を身につけることが、これからの英語学習に求められている。
国際語としての英語は、君たちの必需品になる。
学習の秘訣は、学ぶことは生きること Learning is Living だ。積極的に学んでいこう。
学院長 筒井保明
いまの君は、自分が考えている自分だ。
You Are What You Think.
どうして、彼はあんなに自信に満ち溢れているのだろうか?
毎日、きちんと努力しているからだろうか?
それとも、成功体験をたくさん積み重ねているからだろうか?
他人のことをあれこれ詮索しても仕方がないけれど、自信を持っている人物を見ると、うらやましくなってしまう。私となにが違うのだろうか?
自信というのは、自分を信じる気持ちのことだ。
自分というのは、いうまでもなく自分自身なのだから、その自分を信じるのに、じつは理由や根拠はいらない。「私はできる」「私はすばらしい」そう思えば、いいだけのことである。
自分のことを肯定的に考えるか、否定的に考えるか。たったこれだけのことで君の人生自体が変わってしまう。なぜなら、いまの君は、君が考えている自分だからだ。
人は内心で自分自身と対話している。英語で、セルフ・トーク(Self-talk)という。たとえば、失敗したとき、「しまった!」と一人で声を上げるのも、セルフ・トークだ。鏡に向かって髪を梳かしているとき、「俺ってカッコいいかも」というのも、机に向かって学習しているとき、「私は数学が得意かも」というのも、セルフ・トークである。できれば、このセリフから、「かも」を捨てて、「俺はカッコいい」「私は数学が得意」と言い切れると、本当にそうなる。
ところが、「俺はカッコ悪い」「私は数学が苦手」という否定的な言葉を口に出していると、こちらが実現してしまう。
否定的な言葉は、君の力を台無しにする。最近の研究発表では、「私は年を取り過ぎている」と否定的な言葉を口にする老人と、「私は元気だ」と肯定的な言葉を口にする老人が共に体を鍛えると、前者はあまり改善が見られなかったが、後者は顕著な改善が見られたそうだ。
もし、目の前に深い河があるとして、「渡れるぞ」と自信を持って渡るのと、「渡れないよ」とびくびくして渡るのと、どちらが成功する確率が高いだろうか?
「渡れるぞ」という自信は、人の潜在能力を引き出すことができるが、「渡れないよ」という自信のなさは、持っている能力さえ押さえこむ。だから、うまくいくのは、自信がある方なのだ。
学習も同じことで、「できる」と自信を持って取り組んでいけば、必ずできるようになる。ところが、「できない」と思い込んでいると、できない状態が長く続く。
「できる」と思っている方は、できる状態を望んでいるから、できるようになる。「できない」と思っている方は、できない状態を無意識のうちに望んでいるから、なかなかできるようにならない。
君が、君を信じるのに、理由も根拠も遠慮もいらない。自信は、セルフ・トークを肯定的にすることによって、生まれてくる。「俺はできる」「私はできる」が正解だ。
「人事を尽くして時節を待つ」という言葉がある。やることをやったのだから、あとは成功を待つだけだ。もちろん、時節が合わず、うまくいかないこともあるが、長い目で見れば、将来に成功が持ち越されたと見るべきだろう。
学院長 筒井保明
夏休みの革命
Anything is possible.
革命などというと、名誉革命とかフランス革命とかロシア革命とか、政治体制をひっくり返すような出来事を思い出すかもしれない。あるいは、産業革命とか、エネルギー革命とか、IT革命とか、世界を改めるような出来事を思い出すかもしれない。
いずれにせよ、「比較的短期に起こる根本的変化」のことを革命と呼ぶとすれば、夏休みのあいだに、自分自身に革命を起こすことはじゅうぶんに可能だろう。
夏休みの革命とは、どんな革命か?
夏休みの期間を通して、自分の現状を大きく変化させることだ。夏が終わるとき、自分の目の前の世界が大きな可能性で輝いて見えるようであれば、夏休みの革命は成功したといえるだろう。
では、自分に革命を起こすためには、どうすればいいのか。
まず、可能なかぎり大きな夢や希望を抱いてみよう。
どんなに大きくてもかまわない。世界のさまざまな要素によって私たちはつくられているし、私たち自身も世界を構成している要素にほかならないのだから、私たち一人ひとりは、いつでも世界にとって重要なのだ。(ムダな生命というものはない)だから、君が大きな夢や希望を抱くことは、世界にとって望ましいことである。
つぎに、大きな夢や希望までの道のりをイメージして、いまの自分がどうあるべきかを考える。学問であっても、スポーツであっても、芸術であっても、学び続ける意志がなければ、前途を切り開くことはできない。その事実を、しっかりと見つめよう。
すると、自然に「学びたい」「練習したい」「取り組みたい」という気持ちになってくる。猛然と「学びたい」「練習したい」「取り組みたい」という意志がわきあがってくる。
君の世界は、君の意志である。
夏休みという時間は、小学生にとっても、中学生にとっても、高校生にとっても、本当に重要な時間だ。たんに自由な時間が長いということだけでも、その時間は、君にとって可能性を育む時間になる。なぜなら、人は、強制された時間よりも、自分の意志で取り組む時間に、より大きく成長するからだ。
夏休みの計画をつくるとき、将来の自分の夢や希望を思い描いたうえで、「いまの自分がどうあるべきか」を考え、スケジュールを埋めていこう。すでに、君は、「学びたい」「練習したい」「取り組みたい」と思っているだろうから、計画はすぐにできあがるだろう。
毎日、積極的に取り組むことができれば、自分がみるみる成長していくのがわかる。
さあ、自分に対して、夏休みの革命を起こそう。
学院長 筒井保明
目標に向かって、まっすぐな気持ちで学んでいこう。
I will learn for my future self.
夏期講習のタイトルを「目標に向かって、まっすぐな気持ちで学んでいこう!」とした。いうまでもなく、自分の「目標」を持つことが君の学習のスタートだ。だから、夏休みの前段階で、学習の目標を立ててほしい。未来にむかって、とてつもなく大きな目標を立ててもかまわないし、あるいは、とりあえず、9月が始まったとき、これまでの学習が得意になっている自分の姿を目標にしてもかまわない。算数や数学の問題がすらすらと解ける自分でもいいし、英語の教科書のどの部分であっても口に出して言える自分でもいい。一言でいえば、「できる自分」を想定しておくのだ。
そもそも「できない自分」というものはない。「できる」と意志する方向に人は発達するようにできているのだから、君に必要なのは、君が意志する方向、つまり、目標なのである。
たとえば、登校中、友だちとカレーの話をした君は、どうしてもカレーが食べたくなる。夕食をカレーと決めた君は、家に帰る途中で、必要なお店に立ち寄る。タマネギやニンジンやジャガイモを買い、肉を買い、そして、カレー・ルーの棚の前で立ち止まる。どれを選ぶべきなのか。テレビのコマーシャルが君の頭に次々と浮かぶ。君はそれぞれを手に取って解説を読み、必死に考え、「これだ」というカレー・ルーを買う。
さて、家に帰り、タマネギ、ニンジン、ジャガイモ、肉を切って、油でいため、君は手順通りにカレーをつくっていく。鍋の中に具材を入れ、お湯が煮立ち、頃合いを見て、カレー・ルーを入れる。君はカレーができあがるのを期待して待つ。
じつは、君の目標とは、君が期待して待つカレーと同じものだ。君は、君の目標を、カレーをつくるように、手順を決めて仕上げていく。9月の最初が期限だとすれば、それまでに仕上がるように、準備し、念入りに作業を進めるのだ。仕上がりのイメージがはっきりしていれば、たいていそのとおりになる。(ただし、料理と同じで、調理法をあやまると失敗するので、基本は教わらなければならない。)
以上のことでわかるように、人の行動は、未来の目標によって、決まってくる。目標がなければ、人の行動は行き当たりばったりで、そのときの感情で行動が選ばれてしまうけれども(たいていは、手軽で楽しいものが選ばれてしまう)、目標があると、目標を達成するための行動が選ばれる。
「まっすぐな気持ち」というのは、かんたんなことだ。君が心から望む目標であれば、迷うことなく、君は、まっすぐな気持ちで取り組める。
カレーを食べたいと思った君は、迷いながらカレーをつくらない。目標を達成したいと思った君は、迷いながら学習しない。ほんとうに達成したい目標なら、君は、つまらない誘惑に負けることなく、自然に学習に取り組んでしまう。
まず、自分の目標について考えよう。
そして、目標に向かって、まっすぐな気持ちで学んでいこう。
学院長 筒井保明
ゆっくりと急げ!
Festina lente! Make haste slowly.
「ゆっくりと急げ」という格言がある。ローマ帝国の初代皇帝アウグストゥス(B.C.63-A.D.14)が好んだ言葉で、ラテン語でフェスティナ・レンテと読む。Festina⇒Make haste(急げ)、Lente⇒slowly(ゆっくりと)である。
「ゆっくりと急げ」などというと、君たちは、「急ぐときでもあわてるな」とか、「落ち着いて急ぎなさい」とか、あるいは、「急がば回れ」などと考えるかもしれない。言葉は状況の中で意味が変化するから、どれも正しいのだけれど、「ゆっくりと急げ」を体現して見せたのが、イソップ物語の亀である。
「野兎が亀の遅い歩みをからかって、自分の足のスピードを自慢した。亀は競走を持ちかけて、勝ってみせるよ、といった。じゃあ、勝負だ。
狐が審判になって、彼らは走り出した。野兎は風のように駆け出して、ずっと前方で、笑いながら亀が見えるのを待った。ずいぶん待っても亀が見えないので、『勝負は決まったな、道端の草の上で一眠りしよう』といった。一方、亀は、止まらずに、着実に、ゆっくりと走り続ける。
野兎が目覚め、驚いて、道を駆け下りた。でも、遅かった。ゆっくりとした亀は、最後のラインを越え、競走に勝った。
教訓:長い道のりでは、ゆっくりでも確実なことが、最も速い方法だ」(『イソップ物語』より)
誰もが知っている話である。君たちがここで注意しなければならないことは、「ゆっくりと」には「確実に」の意味が込められているということだ。
このイソップの寓話は、目標を達成する方法を示している。たいていの目標には期限が付いているから、私たちは「急がなければならない」のだ。受験生ならば、痛切にそう感じているだろう。でも、最初の勢いばかりで、野兎のように油断してしまうと、目標にはたどりつかない。世にいう三日坊主とは、この野兎のことである。
亀は、野兎に対して「勝ってみせるよ」といった。誰が見ても勝てるはずのない勝負である。じつは、このとき、亀が見ていたのは、目標と目標に到達する自分のことだけで、野兎など、そもそも眼中にない。(もし、野兎に関心があったら、遠く走り去っていく野兎を見て、自分が走ることをあきらめただろう。また、油断して寝ている野兎を追い越すとき、感情を動かしたはずだろう。)
野兎のことなど一切気にせずに、亀は、目標を達成するために、ゆっくりと走り続けた。
亀は、目標を持ち、目標を達成しようとする人の象徴だ。
野兎は、やみくもに走り出し、途中で歩みを止める人の象徴だ。
さて、「ゆっくりと急げ」という格言を念頭に、フランスの作家ラ・フォンテーヌが「野兎と亀」を書き直した。もちろん、野兎は亀を大きく引き離し、途中で、余計なことに興じて、居眠りを始める。一方の亀は、出発し、コツコツと努力し、ゆっくりと急いだ。
勝った亀が、最後に次のようにいう。
「わたしが正しかったでしょ。速度が役に立ったかしら? わたしの勝ちね。そのうえ、もし、あなたが家を背負っていたら、どうなっていたかしら?」
亀のいう「家」が比喩なのか皮肉なのかわからないけれども、「ゆっくりと急げ」の意味は理解できるだろう。目標に向かって出発したら、君たちは、ゆっくりと急がなければならない。
学院長 筒井保明
やる気は、君のなかにある。
Do you have motivation?
「先生、どうしてもやる気になれないのですが、どうしたらいいのでしょうか?」
1学期が始まって、「この学年こそ成功の一年にするぞ」と誓っている生徒たちが、なぜか、やる気になれないという悩みを持って、相談に来る。
「やりたい」と本気で思っていれば相談に来ないのだが、「やらなければならない」という義務感になってしまっている生徒たちは、その義務を重く感じて、なかなか、やる気になれない。やりたいゲームはいくらでもできるのに、やらなければならない学習は「元気」を挫いてしまうわけである。
そもそも「やる気」って、なんだろう?
「気」がつく熟語や慣用句は、ちょっと調べればわかるように、とても多い。
もともと「気」とは、「物より発する微妙不可思議なもの」である。幸田露伴の説によれば、「その物の気は、即ちその物の本体と同一にして、あたかも本体の微分子なるがごとく、(中略)気あれば必ず物あり、物あれば必ず気あり、気と物と相離るれば即ち物すでに物たらず、物と気と相失えば即ち気すでに気たらず。」である。
水の上に手をかざせば、湿り気を感じる。火に手をかざせば、熱を感じる。これも「気」である。露伴先生は、「気」に相当するやまとことばは「にほひ」(色、声、光、容姿など、その物から感じられるものは、すべて「にほひ」)だという。天に天の気、山には山の気、海には海の気、酒には酒の気、茶には茶の気、軍隊には軍隊の気、春には春の気、人には、人の気があるのだ。(一切万物に一切万物の気あり)
さらに、やまとことばで「気」は、「いき」。「いき」は、「いのち」となり、「いぶき」となり「いきおい」となり、「いきる」「いきりたつ」「いきつく」「いきごむ」「いきまく」などとなる。
つまり、生きている君自身が発するものが「気」であり、「やる気」とは、なにかをやっている君自身の「気」のすがたのことだ。だから、「やる気」を感じるのは君自身でなく、君を「やる気のある生徒だなあ」と見る他の人たちである。
最初の質問に答えれば、君がなにかをやらないかぎり、「やる気」は存在しない。君がやる気になれないのは、「やりたい」と思えないからで、「やらなければならない」と重荷に感じているからだ。「やらなければならない」は、「できればやりたくない」を引き起こしてしまう。「やりたい」と思えば、放っておいても、やる気になってしまう。
まず「やる気になれない」ときには、もう一度、目標を見直してみよう。そして、自分に問いかけるのだ。「これは、本当に自分が達成したい目標なのだろうか?」
じっくり考えて、「やっぱり、達成したい!」という自分を発見できれば、誰かに背中を押されなくても、君は、自然に学習に取り組んでしまう。
「やりたい!」⇒「なにもいわれなくても、自分から取り組んでしまう」
これが、「やる気」の正体だ。
しっかり目標を持つことができれば、5月病など、どこ吹く風である。
元気に前進していこう。
学院長 筒井保明
「温故知新」に未来の答えがある。
Gain new insights through restudying old material.
小学校、中学校、高校で、新年度が始まる。
書店には、辞書、参考書、問題集、学校案内、ノウハウ本など、おびただしい学習関連・受験関連の書籍が積み上げられている。
立ち寄って眺めてみるけれど、購入したくなるような本はわずかだ。
学習関連・受験関連の書籍は、入れ替わりが激しく、古いものが新しいものに取って代わられている。しかし、毎年、「まてよ」と思う。かつて私が感動した名著は、書店に並べられることがない。
『論語』の一節に、「温故而知新。可以爲師矣。」とある。学校教育的には、「ふるきをたずねて、あたらしきをしれば、もってしたるべし。」と読む。しかし、唐話(中国音でそのまま読もう)を主張した荻生徂徠(1666-1728 漢学者)の弟子たちは、当時の唐音で※「ウヲンクウル、ツウスイン…」(温故而知新)と読んだろう。いまだに学校では漢文訓読法を実施しているが、私は、漢文を教えはするけれど、できれば荻生徂徠に従いたい。江戸時代、川越の顧問でもあった荻生徂徠は、漢文訓読法という不自然な方法がいやだったのだ。
この不自然さは、翻訳作業のような、現在の英語学習にもいえる。英語教育に関する話題が依然としてかまびすしいけれども、ほとんど結論は出ていると思う。
英語教育に関していえば、多摩大学名誉学長のグレゴリー・クラーク氏の言っていることが正しいと私は考えている。クラーク先生の『英語勉強革命』という著書からポイントを抜き書きしてみよう。
「語学は“聞く”ことに始まる」
「Use it or lose it.(使わなければ、失ってしまう)」
「日本人は語学に関して努力不足」
「外国語を覚えようとしたら、その言葉を意識、無意識の両方の領域に入れなければならない」
「文字を見ずに一生懸命に何度も聞く」(聞き流さない!)
「自然会話をする」
「耳できいた文章をテキストを見ながら音読する」
「言葉は無意識レベルで覚えなければならない」
「カタカナ英語は厳禁」
「発音は耳で覚える」
古代トロイアの遺跡を発掘した考古学者のシュリーマンも、日米和親条約の締結に尽力したジョン万次郎も、語学習得の方法は、結局のところ、変わらない。
「温故知新」という言葉を噛みしめるとともに、新しい学年でたくさんのことを学んでいこう。
※当時の唐話の本による推測。
学院長 筒井保明