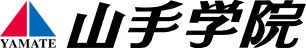夢は実現する
Dreams come true!
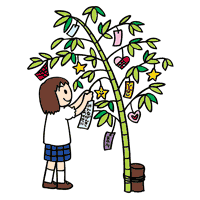
七夕の夜、君も、願いごとを書いた短冊を笹の葉につるしただろうか。
短冊に書かれた願いごとは、それが本気の目標であり、君の良心に反しない希望であるならば、きっと実現するだろう。なぜなら、君が信ずるかぎり、夢は実現するものだからだ。
では、「夢は実現する!」を科学的に解説してみよう。
そもそも夢とは「君が実現したいこと」である。
本気で「実現したい」と思うと、行動を促すホルモンであるドーパミンが君の脳の前頭前野まで届き、君は行動を起こすことになる。つまり、「君の夢」は、行動のモチベーションなのだ。
つぎに「実現したいこと」に関連する情報が、どんどん君のなかに飛び込んでくる。情報の取捨選択は、君の関心によって決定される。君が関心を持っていることは、あちこちから君の目や耳に入ってくるけれど、君が関心を持っていないことは目の前にあっても馬耳東風で君を素通りしていくだけだ。「実現したいこと」があると、それを達成するために必要なことがわかってくる。ものごとは、目標が先で、手段は後から見つかる。これも脳の働きの一つ。
さらに「実現したいこと」につながる取り組みは、すべて君にとって「やりたいこと」になる。「やりたいこと」をやるとき、君の脳の海馬や前頭前野が活性化して、スムーズに取り組みを進められる。そして、君は自分が満足するまで取り組みを続けられる。
このように、毎日、自発的に、積極的に取り組んでいくことができれば、夢は実現するだろう。
ところが、君の夢の実現を妨げようとするものが、つぎつぎとあらわれる。
それが保護者であったり、先生であったり、友だちであったりすると、君は困惑してしまう。
教育学者のマリア・モンテッソーリは、「子どもの能力の発展を妨げているのは、ほかならぬ教師である」といった。「やさしい教師の、おせっかいな手出し、不必要な指導が、子どものやる気を削ぎ、自発的な取り組みを阻み、大きな成長の機会を失わせているのだ」と厳しく指弾した。
モンテッソーリが見た事実として、「子どもたちがなにかを取り囲んで、わいわい騒いでいた。その集団の後ろで小さな子どもが背伸びをしているが、のぞき込むことができない。そこで、その子どもは、その場所から離れ、椅子を運んできた。椅子の位置を決め、椅子の上に立って、その子どもは、ぐんと背を伸ばそうとした。そのとき、その子どもの行動に気づいた教師が、子どもをうしろから抱きかかえ、のぞき込める高さに持ち上げて、さあ、これで見えるでしょ、といった。自分の行動を中断されたときの、小さな子どもの、ざんねんな、がっかりした表情といったら!」
一つの秩序をつくろうとして、子どもは自分で取り組んでいた。しかし、教師のおせっかいが、取り組みを中断させ、秩序をつくる(学習する)喜びを子どもから奪ってしまった。思いやりのある教師でも、このようなまちがいを仕出かす。やがて、子どもは、自発的な取り組みをやめてしまう。
目標達成法のなかに、「自分の夢や目標を周囲に話してはいけない」という項目があるのは、この教師と似たような行動をとる人が多いからかもしれない。悪意の妨げは撃退するだけだが、善意の行為は防ぐことがむずかしい。もちろん、人の助けが必要なときもあるから、周囲の人には、
「助けが必要なときは、相談します。だから、自分一人でやっているときは、どうか見守っていてください」と頼んでおくといいだろう。
ともあれ、本気の夢は実現するものだ。さて、君の夢はなんだろうか?
※Dreams come true.と夢が複数であるのは、君の夢はいくつもあるはずだから。
学院長 筒井保明
積極的な心と態度
Positive Thinking and Attitude
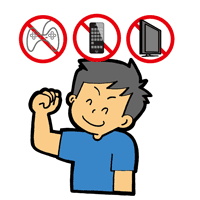
夏期講習のパンフレットの表紙の言葉を「成長の夏、実行の夏。自分の力を信じて積極的な心と態度で取り組もう!」とした。英語で「積極的な心の態度positive mental attitude」というので、「心の態度」も考えたが、「心と態度」に決めた。なぜなら、心の態度attitudeが変わると、行動の態度behaviorも変わるからだ。わたしたちが使う「態度」という言葉には、どちらの英語の意味も含まれている。
さて、君は、どんな夏を過ごそうと考えているだろうか?
わたしは、この夏が、君にとって「成長の夏、実行の夏」になることを願っている。
そして、「成長の夏、実行の夏」を実現するために、「自分の力を信じて、積極的な心と態度で取り組もう!」と君を強く励ましたい。
あとは、君が「やるぞ」と自分に気合を入れて、行動を起こせば、君自身でも信じられないような力がわき上がってくるだろう。
夏とは、そういう季節なのだ。この夏の特性を生かすことは、君にとって重要なことである。
今年は、山手学院の45周年にあたるため、いろいろな校舎の保護者会や公開講座で、山手学院の教務部の責任者や室長たちといっしょに入試分析や学習法や合格必勝法などを語っている。
おもしろく、楽しく聞いてもらうために、毎回、ポイントは変えているが、学習法自体はほとんど変わらない。(コロコロ変わったら身につけられない)
ところが、学習法などより先に、君たちは「生活習慣」を身につけなければいけない。
「生活習慣+学習=学力」というのが、わたしの主張である。
もし君が就寝前にテレビやパソコンやスマートフォンなどに時間を使っているようであれば、電子機器の光によってメラトニンの分泌が妨げられ睡眠が浅くなってしまう。そして、こわいことに、君の脳や体を成長させ、傷ついた細胞を修復し、疲労を回復させる成長ホルモンが分泌されなくなってしまう。朝、起きられない。体調がよくない。やる気が起きない。これでは、学習どころではないだろう。
さらに、睡眠前の記憶は、テレビやパソコンやスマートフォンなどの情報によって、壊れることがわかっている。だから、わたしは、「ご褒美テレビ」のような、学習後に別の情報をぶつけることのマイナスを説明し、さらに受験生を中心に、「就寝前は、電子機器の使用禁止。手短にまとめ学習をしてから、リラックスして積極的な気持ちで(できると信じて)ぐっすり眠る」を強く勧めている。
実際にやってみると、多くの生徒たちが、「朝、起きたとき、すべておぼえていました」「どんどんできるようになりました」「記憶が楽になりました」「短時間でできるようになりました」「学習に自信が持てました」などと、異口同音に報告してくれる。記憶と睡眠はセットであるから、当然である。
そして、かれらが報告してこない(気づかない)もっとすぐれた効果がある。それは、かれらが「積極的な心と態度」を強化していることだ。
睡眠時の脳波は、リラックス・浅い眠り・レム睡眠におけるアルファ波・シータ波から、深い眠り(熟睡状態)・ノンレム睡眠におけるデルタ波を往復する。このとき、記憶だけでなく、自己イメージも書き込まれる。いいかえれば、積極的な気持ちでぐっすり眠れば、積極的な気持ちで起きられるようになる。
なにごとも論より証拠だから、この夏のあいだ(今日からでもいい)、「自分の力を信じて積極的な気持ち」で就寝して、「積極的な気持ち」で、朝、起きてみよう。
きっとさまざまなことがうまくいくようになるだろう。
学院長 筒井保明
もっとも重要な時間
The most important time
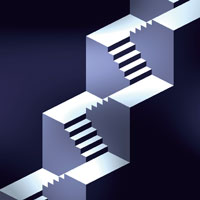
「もっとも重要な時間The most important time」を英語で検索したら、アメリカの公民権運動を指導したキング牧師のテレビ・インタビューが表示された。
わたしとしては、ぜんぜん違うことを予期していたのだが、思わぬものがあらわれた。
キング牧師のインタビューを抄訳すると、
「いまが、自分の人生を決める重要な時だ。問題は、君が、本質的な、固い、健全な計画をもっているかどうか。君の計画に必要なもの、一つ目は、自分という威厳、自分という価値、自分という人物に対する深い信念だ。他人は関係ない。二つ目は、原則として、君が取り組む様々な分野で、すばらしさを達成する決意だ。あくまで自分がどうするか、自分で決めていく。樹になれないなら、茂みになれ。公道になれないなら、畦道になれ。太陽になれないなら、星になれ。サイズなんて、関係ない。君がなれるもので、ベストになれ。三つ目は、真善美の永遠の原則に従うことだ。いわゆる豊かな人生は、水晶の階段で、わたしたちのものじゃない。でも、わたしたちは、動き続けなければならない。進み続けなければならない。君が飛べないなら、走れ。君が走れないなら、歩け。君が歩けないなら、這え。なんとしてでも、動き続けろ」
水晶の階段crystal stairという言葉は、ラングストン・ヒューズという黒人の詩人の「母から子へ」のなかの一行「わたしにとって、人生は、水晶の階段じゃなかった」を踏まえている。ヒューズの詩もすばらしい。最後の連だけ訳すと、
「振り返っちゃいけない。つらくても、階段に腰を下ろしちゃいけない。いま、くじけちゃいけない。なぜなら、お母ちゃんだって、まだ進んでるんだ、かわいい子よ、お母ちゃんだって、まだ登っているんだ。わたしにとって、人生は、水晶の階段じゃなかったけどね」Mother to Son by Langston Hughes
水晶の階段は、階段の踏み板の表面に水晶が散りばめられていたり、階段の手すりが透明なクリスタルであったり、手すりを支える親柱や柱が水晶であったり、階段全体がキラキラしていたりするような、とても豪華な階段だ。この階段をのぼるのは、白人の富裕層にちがいない。
いっぽう、公民権運動で全米が揺れ動いていたとき、黒人たちは、鋲が出て、木の破片が散らばる、ボロボロになった板きれの、カーペットのない、むき出しのままの踏み板の階段をのぼり続けていた。そして、一つの踊場にたどり着くと、角を曲がって、また、ガタピシした階段をのぼり続けていたのだ。真っ暗闇に入りこんだことも一度や二度ではなかった。ヒューズの比喩を使ったけれど、黒人たちの苦難が想像できるだろうか。
苦難を前にして、キング牧師は、「自分の人生を決める重要な時だ」といった。
自分という威厳、自分という価値、自分という人物に対する深い信念は、すべての人にとって最初に必要なものである。
君も自分の目標に取り組むとき、まず、この信念があるかどうかを問うてみよう。
自分という威厳とは、容易に左右されない自分の態度のこと。
自分という価値とは、容易に左右されない自分の心のこと。
自分という人物とは、容易に左右されない自分自身のこと。
さあ、信念を持って、目標につながっている「自分の階段」をのぼっていこう。
学院長 筒井保明
友だちとともに学ぶ。
Learn in the company of friends.
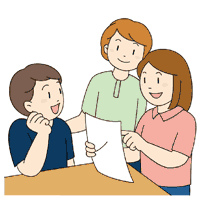
アクティブ・ラーニングという言葉を聞いたことがあるだろう。
アクティブは能動的ということ。その対義語は、パッシブで受動的ということ。
脳の機能でいえば、「見るだけ・聞くだけ」の学習はパッシブで、自分の口や手を動かす学習はアクティブということになる。
パッシブな学習における学習内容の定着率は低く、アクティブな学習における学習内容の定着率は高い。だから、君たちは、積極的な態度で、自分の口や手を動かしながら、どんどん学習しよう。
さて、世界中で学習に関する仮説と検証が毎月のように発表される。研究というのは厳しいもので、その多くは、すでに研究され、結果が公表されているものを追認しているものばかりだ。本当に新しい研究というものは数少ない。
たとえば、「読書量が増えれば増えるほど、算数・数学が得意になる」という調査結果は、くりかえし発表されている。どの調査も「読書好きの子どもは、算数・数学が得意になる」という結果になっている。当然といえば当然で、読書は「言語という抽象概念」を読み取ることであり、算数・数学は「数字や記号という抽象概念」を操作することであるから、脳の働きとしてはほぼ同じなのである。読書に秀でることは、算数・数学に秀でることに通じるのだ。
もしかしたら、君たちのなかに、「ぼくは理系」とか「わたしは文系」とか、なんとなく教科の好き嫌いで自分を規定している生徒がいるかもしれないけれど、人の能力として「理系」とか「文系」という性質はない。能力ではなく、じつは「好き嫌い」である。
その証拠に、20世紀最大の知性といわれたポール・ヴァレリーというフランスの詩人は、生涯にわたって数学に取り組んでいたし、人工知能の父といわれたマーヴィン・ミンスキーというアメリカの科学者の文章はすばらしい。こういう人たちの業績に接すると、「理系」とか「文系」という性質が存在しないことがわかる。『ファウスト』や『若きウェルテルの悩み』で有名なゲーテは、19世紀の最高の詩人であり、劇作家であり、色彩論、形態学、生物学、地質学を研究した科学者であり、さらに政治家であった。どこに「理系」と「文系」が存在するだろう?
「理系」と主張する君。もしかしたら、音読・読書を怠ってしまって、読書をさぼっているだけではないか?
「文系」と主張する君。もしかしたら、計算練習を怠ってしまって、算数・数学を毛嫌いしているだけではないか?
「理系」が好きな君は、たくさん読書することによって、もっと理系教科・科目のことが理解できるようになる。
「文系」が好きな君は、算数・数学に取り組むことによって、もっと文系教科・科目のことが理解できるようになる。
どの教科・科目も、人の教養としてつながっているのだから、小学生・中学生は、どの教科・科目にもしっかりと取り組まなければならない。
君たちは、たくさんのことを学び、たくさんのことを身につけているうちに、やがて、友だちや仲間とそのことについて語り合ったり、論じ合ったり、教え合ったりしたくなるだろう。
本当のアクティブ・ラーニングは、この時点から始まるのだ。
学院長 筒井保明
自分を選ぶ!
Choose yourself!
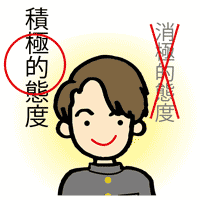
人は自己イメージに従って行動する。
「できる」と思っている生徒は、できるように行動するし、「できない」と思っている生徒は、できないように行動してしまう。
だから、最初から「自分はできる」と決めて、あらゆることに取り組めばいいのだが、うまくいかない生徒も多いだろう。
「できる・できない」は、「積極的態度・消極的態度」といいかえてもいい。積極的態度で取り組むと、できるようになるし、消極的態度で取り組むと、なかなかできるようにならない。
君の態度が「積極的か・消極的か」ということは、君の人生を左右する本質的な問題である。
では、なにが君を積極的にし、なにが君を消極的にするのだろう?
答えは、君自身の選択だ。君が積極的な自分を選べば、積極的態度になり、君が消極的な自分を選べば、消極的態度になる。
君は、君自身が選んだ自己イメージどおりの君なのだ。
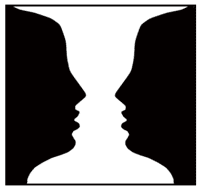
たとえば、有名な「ルビンの壺」の図柄を見てみよう。
最初はたんなる白黒の図柄である。しかし、見ているうちに「壺」を見た君は、この図柄から「壺」というイメージを選んだのであり、「向き合う人たち」を見た君は、「向き合う人たち」というイメージを選んだのである。
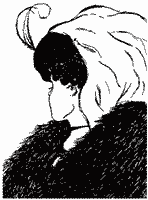
つぎの絵は、どうだろう。「老婆」を見た君は、「老婆」を選んだのであり、「若い女性」を見た君は、「若い女性」を選んだのである。専門的には「ゲシュタルト」というけれど、君の頭の中でつくられたイメージ(意味のある全体)が「老婆」になり、「若い女性」になる。そして、イメージを選択するのは、君だ。
これは視覚の例であるけれど、人はあらゆる現象に対して同じことをおこなう。
だから、君という複雑な存在に対して、君はいろいろな自分を選択して思い描くことができる。本来、君は積極的でも消極的でもない。そのままの君だ。
ところが、君は、自分のことを積極的だと思ったり、消極的だと思ったりする。つまり、そのままの君の中から、積極的な自分を選んだり、消極的な自分を選んだりしている。
そうだとしたら、自分の目標を達成したい君が実行することは、「積極的態度の自分」を選ぶことだ。積極的態度で「できる」と信じて取り組むならば、たいていのことはできる。
しかし、長年の習慣で、どうしても「消極的態度の自分」を選んでしまうようなら、「積極的態度の自分」を自然に選ぶようになるまで、自分を訓練しなければならない。
具体的には、君が「できるようになりたい」と願っているたくさんのことのうち、すぐ目の前の「いま、できないこと」を意識して、できるようにする。すると、「できること」が君に一つ加わる。これをしばらくのあいだ、くりかえしていると、君の潜在意識に「できる」という事実が積み重なっていく。小さな「できる」の積み重ねが、やがて大きな変化を起こす。君は、いつでも「できる自分」を選ぶようになる。
自分の目標を達成するために、新学年の学習に積極的態度で取り組んでいこう。
学院長 筒井保明
自分の道を進もう!
Go your own way!
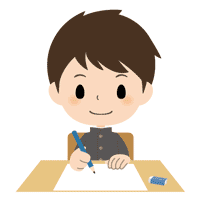
入学試験には、合格と不合格がある。解答に対して、正解と不正解がある。記述問題のように、正解と不正解のあいだという場合もあるが、それでもすべてが得点化され、入学試験の結果によって、合格、不合格が決められる。
受験生を指導する立場でいうと、目に見える得点以外に、やる気や情熱や志を評価してもらいたいと心から思う。募集定員がある以上、競争はやむを得ないのだが、それでも、君たちのやる気や情熱や志を評価しないのはもったいないように感じる。なぜなら、本当に重要なのは、入学後の取り組みだからだ。
入試直前になると、受験生のみんなに、どんな言葉をかけるべきなのか、やはり悩む。これまで生徒たちにたくさんの励ましやアドバイスの言葉をかけてきたけれど、入学試験に立ち向かう直前にふさわしい言葉はなんだろうか?
それぞれの志望校合格に向けて、かけてきた時間量はずいぶん違うだろうけれど、「この学校に行きたい」「この学校に合格したい」という気持ちに違いはない。そうだとすれば、入試当日において、自分の道を進んでいこうとする君たちに求められるのは、「平常心」である。
これまで培った自分の力を出し切るためにも、「平常心」で試験問題に取り組んでほしい。余計なことを考えずに、試験時間中は、試験問題に全力を注いでほしい。
入学試験は人生の通過点の一つだけれど、そこに全力を注いだかどうかは、その後を左右するだろう。結果として、どの学校に進んだとしても、入学した学校から、君は、もっと大きな、未来の目標に向かって、進んでいく。君の人生は、学校が決めるのではなく、君が自分で決めるのだ。
「平常心」は、禅宗の最も重要な言葉の一つ。
禅宗の公案を集めた書物『無門関』に「平常是道」という文章がある。
師匠の南泉和尚に、趙州和尚が質問した。
「道って、なんですか?」
南泉和尚が答えて、
「平常心が、道だよ」
「それじゃあ、平常心という道に向かっていくべきですか?」
「平常心に向かおうと意識してもだめだね」
「意識しなかったら、平常心かどうかわからないじゃありませんか」
「道は知ることでもないし、知らないことでもない。知ったと思えばまちがうし、知らなければそれだけのこと。もし、本当に、疑わない道(平常心)に達したなら、宇宙万物は、わだかまりなく、深く広いものだ。論ずる必要もないよ」
そういわれて、趙州和尚は、たちまち悟った。(無門関十九)
疑わない道が平常心である。この場合、疑わないというのは、「いま、ここにいる、自分」という存在のことだろう。いかなる場合にも、「平常心」であることを禅宗では求める。
さあ、入学試験会場で、開始時間が近づいたとき、ゆっくりと呼吸して、リラックスしよう。そして、自分を疑わずに、全力で取り組もう。
君は、いつでも自分の道を進んでいるのだ。
学院長 筒井保明
未来の自分が、本当の目標だ!
Your Future Self

小学生、中学生、高校生、それぞれの最終学年に受験生がいる。入試日が近づいているので、一様に緊張が高まっているようだ。大学受験生のなかにはすでに推薦入試で合格した生徒もいれば、不合格に涙した生徒もいる。
先日、山手学院高校部の大学受験生と話をした。第一志望の国立大学の推薦入試は不合格であったけれど、これから一般入試に向けて、全力で受験学習に取り組むと決意を語ってくれた。
「推薦入試は、調査書20点・小論文40点・面接60点の合計120点満点の審査で、すべてベストを尽くしましたから、後悔はないです。高校の先生は、一般入試では無理かもしれない、浪人の覚悟が必要だ、というのですが、わたしはあきらめません。一般入試でかならず合格します」
彼の名誉のためにいっておくと、彼が受験した国立大学教育学部の教科教育コース専修の推薦入試は、募集人員3名である。おなじ志を持つライバルたちと競うのだから、わずかな差で合否が分かれる。彼の力量不足ではない。
彼が志望する国立大学の全体としてのアドミッション・ポリシーは、
①(知識・技能)専門分野の学修に必要な基礎学力を有していること。
②(知的関心)地域の事象、自然環境、国際社会、人間と多様な文化等の広い分野に対する知的関心を有していること。
③(思考力・判断力・表現力)他者とともに課題解決を目指した経験があり、そのための基礎的な思考力・判断力・表現力を有していること、あるいは、それらを身につける意欲を有していること。
④(主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度)多様な人々とコミュニケーションを取りながら協働して主体的に活動した経験があること、あるいは、そのような活動をする意欲を有していること。
この四つは、すべての大学生に求められる能力・資質といえる。アドミッション・ポリシーというのは、県公立高校でいえば、「本校が求める生徒」である。たとえば、川越高校が求める生徒は、「伝統ある自主独立の精神を自覚し実践する生徒。高い志を立て、その実践に向け常に努力を重ねる生徒。文武において切磋琢磨し自己を高め、優位なリーダーを目指す生徒」だ。
現在、小学生、中学生である君たちも、ゆくゆくは自分の希望に合った大学を目指すことになるだろう。中学受験であっても、高校受験であっても、まず未来の自分を考え、「学びたいこと、身につけたいこと」があるからこそ、君たちは志望校を持ち、受験生になるのだ。
さきほどの高校生が目指す国立大学教育学部は、アドミッション・ポリシーに加えて、入学者の能力・資質として、①各教科についての幅広い知識、②教育への関心と教員になりたいという強い意欲、を求めている。この生徒は、中学生のころから、「教育への関心と教員になりたいという強い意欲」を持ち続け、いま、受験生としてチャレンジしている。将来、彼はよい教師になるにちがいない。わたしは彼が合格することを信じている。
君たちも、未来の自分のことを考えてみよう。君たちの道は未来の自分につながっている。未来から見れば、小学校も、中学校も、高校も、大学も、君が通過してきた場所である。だから、受験生にとっての志望校は、当面の目標であり、突破すべき目標で、どの学校であっても、入学したとき、つぎの目標を目指すための場所に変わる。ほんとうの目標はもっともっと先にあるのだ。
さあ、当面の目標を達成するために、受験当日まで、徹底的に学習に取り組もう。悔いをカケラも残さないくらいに。
学院長 筒井保明
自分を信じよう!
Trust yourself !

お正月を迎え、寺院や神社に出かける機会が増えるだろう。寺院のお御籤や神社の御神籤をひく人もいるだろう。一年の吉凶禍福をうらなうわけだが、吉凶はあざなえる縄のごとしで、裏表でしかない。
「よい」と思えば吉だし、「わるい」と思えば凶である。
日本のおみくじの祖は、第18代天台座主、良源(912-985)。
中国の観音籤が、如意輪観音の化身といわれる良源(元三大師)に託された。
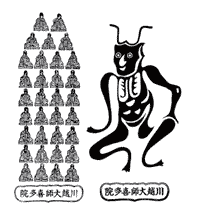 天台宗の大僧正・天海(1536-1643)が住職を務めた川越大師喜多院の護符も良源の変化である「豆大師」(魔滅大師)と「角大師」である。鬼のような姿は、悪魔降伏の行法のとき、良源が変身したものだという。
天台宗の大僧正・天海(1536-1643)が住職を務めた川越大師喜多院の護符も良源の変化である「豆大師」(魔滅大師)と「角大師」である。鬼のような姿は、悪魔降伏の行法のとき、良源が変身したものだという。
元三大師のおみくじは、大吉・吉・小吉・末吉・凶をとりまぜて、一番から百番まで。江戸時代・明治時代の解説書を見ると、くじの引き方のルールが厳しい。まず身を清める。手を洗って、口をすすぐ。香をたいて、観音様を念じて、法華経普門品を読む。呪文を三百三十三回、礼拝を三十三回、おみくじの箱を三度頂戴して、願文を読む。そうして、箱を振って、おみくじを取り出す。
江戸時代・明治時代の人たちが、これを実行して、おみくじを引いていたとは思えないが、ルールはルールである。きちんとやった人もいるだろう。
さて、大吉が出れば、うれしいし、凶が出たら、やっぱりいやだろう。
そこで大吉を一本引いてみる。
第九十番 大吉
一信向レ天飛。(一信、天に向かって飛ぶ。自分を信じれば、天に向かって飛ぶように実現する)
秦川舟自帰。(秦川の舟、おのずから帰る。宝を積んだ舟がもどるように、望みがかなう)
前途成レ好事レ。(前途、好事成る。いまやっていることが必ずいいことになる)
応レ得レ貴人推レ。(まさに貴人の推を得べし。人に推されて、よいほうに向かう)
第一句、生まれてから十五歳まで。第二句、十六歳~三十歳。第三句、三十一歳~四十五歳。第四句、四十六歳~六十歳。六十一歳より、本卦がえりで第一句にもどり、一句に十五年をかける。
したがって、小学生、中学生の君たちは、第一句の「一信向天飛」である。
「一信」は、「一心」であるから、君たちは、目の前のことに全力で取り組めばよい。
自分の目標に向かって、自分の可能性を信じて、一生懸命に取り組んでいけば、天に向かって飛ぶときが来る。大吉が実現する最大の条件が「信じること」なのだ。
もし、おみくじを引いて、凶だったら?
元三大師は通称で、観音様の化身といわれる良源のおくりなは慈恵大師という。おみくじが観音様を本尊にしている以上、凶を引いた人が言動を慎めば、「凶は変じて吉となる」のが道理である。つまり、おおもとは大吉だ。
じつは、くじを引く前の三百三十三回の呪文は、前もって、すべてのわるいことを妨げ、すべての望みをかなえるための呪文である。「おん はら た はん とめい うん。おん はん とま しん だ ま に しんば ら うん」
しかし、呪文などいらない。
君は君自身を信じよう。
学院長 筒井保明
自分の目標を思い描こう!
You must dream your way.

寝ても、覚めても、自分の目標のことを思い描いている。いつも希望に満ちあふれていて、夢中でなにかに取り組んでいる。受験生であっても、自分の目標に向かって、自分の意志で一生懸命に取り組んでいる生徒たちの顔は、苦労の影など少しもなく、引き締まって輝いている。
中学受験生でも、高校受験生でも、大学受験生でも、そんな生徒たちと接するとき、「自分の目標に向かって全力で取り組むことは、自分の内側から可能性を引き出すことにほかならない。だから、彼らは輝いているのだ」という思いにとらわれる。
じっさい、そんな生徒たちを見てもらえれば、わたしのいうことが大げさでないことがわかるだろう。現在の取り組みに自分の意志がまっすぐに通っているから、彼らの学んでいる姿はきれいなのだ。もし自分の意志でなく、どこかの誰かに命令されたのだとすれば、彼らの姿や表情に弛みや翳りが見えてしまうだろう。受験生のだれもが、全力で自分の目標に取り組んで、大きな可能性を引き出すような学習ができることをわたしたちは強く願う。
さて、進学指導が中学校や高校でも本格化する。
志望校選択は、本来、自分の将来を考えて、自分にふさわしい学校を選ぶことだ。
ところが、多くの人たちは、君の「現在の学力」から判断して、君に学校選択を勧めるかもしれない。なるほど、受験まで数カ月ともなれば、どうしても現状を基準にしたくなる気持ちはわかる。
それでも、やはり、志望校は、君の将来を前提に選ぶべきである。君の将来につながる学校は一つではないから、第一志望校、第二志望校、第三志望校…と、あくまで君の将来につながる学校を選んでいく。
君の可能性は、現在の君より大きいのだから、現状にとらわれてしまうと、判断を誤ってしまうだろう。中学受験や高校受験では苦戦したものの、入学した学校で学力をグングン伸ばし、大学受験で第一志望校に合格している生徒たちは本当にたくさんいるのだ。彼らの共通項は、中学受験や高校受験を最終目的とせず、自分の将来を目標にしたことである。将来の目標を見定めていたので、それぞれの中学や高校に入学後、抜群の成績をおさめて、いろいろな中学や高校のパンフレットで成功の秘訣を語ったりしている。以前、星野学園のパンフレットに、一橋大学、お茶の水女子大学、
慶応大学に進んだ生徒たちが並んでいて、三人とも指導した生徒で驚いたことがある。彼女たち(また保護者)は、目先のことにとらわれず、将来を考えて、いくつか学校を選択していた。個性に合うこと、通学時間がかからないこと、学習時間が確保できることなど、さまざまな検討の結果、
星野学園を志望校の一つに選んだ。
受験は、「少年よ。大志を抱け」が基本である。現在の学力を基準に学校を選ぶのではなく、自分の将来にふさわしい、合目的的な学校を選ぶべきだろう。
君の「現状」は、過去によってもたらされたものにすぎない。君は未来に向かう存在であり、これからも目標に向かって成長する。「現状打破」が、君の毎日なのだ。
小さな目標でも、大きな目標でも、人は目標に向かって行動を起こす。
本気の目標がないとき、君の学習は散歩のような状態で、まだまだ道草を食いがちである。
本気の目標があるとき、君の学習はマラソンのような状態で、まっすぐにゴールに向かう。
志望校を決めるとき、まず自分の進む道を思い描いてみよう。
学院長 筒井保明
君の可能性の始まり
The Beginning of Your Potency

前回、学習前の準備として、
①まずゆっくり呼吸しながら体の力を抜いてリラックスする。
②リラックスしながら、学習者として理想的な自分をイメージする。(らくらく問題を解いている姿でも、集中して取り組んでいる姿でも、好ましい自分の姿であればよい)
③思い描いた自分の姿に対して「わたしはできる」と確信を持つ。(できるぞ、と理想の自己イメージに声をかけてもよい)
ということを書いた。さっそく、実践した生徒から質問されたので、答えよう。
(Q)「らくらく問題を解いている自分」「集中して取り組んでいる自分」はイメージできました。そして、その自分に「おまえはできる」と声をかけました。そうしてから、学習を始めたのですが、効果が上がっているのかどうかわかりません。今後、どうしたらいいのですか?
(A)しばらくのあいだ、続ければ、効果がはっきりしてくる。理想の自己イメージにしたがって、実際に問題を解く。集中して取り組む。実際に行動を起こすことが重要なのだ。その行動自体も経験されるので、繰り返して続けることによって、さらに理想の自己イメージどおりの自分になっていく。いわば、セルフ・エデュケーションだね。
自己イメージと行動の関係を考究し、自然療法として実践するフェルデンクライス・メソッドの創始者であるモシェ・フェルデンクライス(1904-1984)は、「何年もかかってできあがった自己イメージにしたがって、誰もが、それぞれのやり方で、話したり、動いたり、考えたり、感じたりする。行動の仕方を変えるためには、自分の中に持っている自己イメージを絶対に変えなければならない」という。行動を変えるためには、現在の自己イメージを変えることがMUSTなのだ。
自己イメージは、静的なものではなく、動作、感情、感覚、思考によって成り立っている。
たとえば、歩きながら、サルをイメージすれば、君は次第に背を丸くして歩くようになる。(もしかしたらキーキー鳴いてしまうかも?)王様をイメージすれば、次第に胸を張って歩くようになる。泥棒をイメージすれば、抜き足差し足で歩くようになる。お嬢様をイメージすれば、内またで上品に歩くようになる。(実際にやってみよう。体がイメージに従うことに驚くはずだ)
さて、これまで学習の取り組みをいやがっていた君が、心機一転、リラックスして、すすんで問題を解くようにする。(解けない場合でも、前向きな気持ちで解こうとする)また、目の前のことに、集中して取り組むようにする。この行動自体が変化であり、これを繰り返して続けていると、この変化が習慣になってくる。変化が習慣として固定したとき、学習嫌いだった君は、どんどんと積極的に学習に取り組む君に変わったのだ。
いやいや学習に取り組んでいれば、それが習慣化して固定してしまう。(そして、学習が苦手な自己イメージができあがる)
気持ちよく学習に取り組んでいれば、それが習慣化して固定してしまう。(そして、学習が得意な自己イメージができあがる)
もし、いま学習が苦手で、これから得意になりたいのなら、これまでにできあがった自己イメージを絶対に変えなければならない。その方法の一つが冒頭の学習前の準備なのである。
フェルデンクライスの言葉を君の励ましのために一つ。
「僕が窮地にいるのを君は目撃した。そして、ここからが僕の可能性の始まりなのだ」
学院長 筒井保明