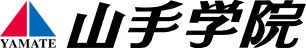「そろばん」という呼び名になった理由
「そろばん」の名の由来について、いろいろなことがいわれています。多くの人が推理していますけれど、答えはそれほどむずかしくないと思います。
答えをいう前に、どのような考えがあったのか、見てみましょう。
「算盤は、珠が揃って並んでいる盤でありますから、揃え盤であります。そのソロエバンという意味から、ソロバンになったのです」
「ソロバンの珠を弾くとき、珠の音がサラサラと聞こえます。サラという音とソロという音は似ていますから、サラサラと鳴る盤というサラバンが、ソロバンに変わったのではないでしょうか」
「算盤は、中国では珠盤ともいいます。シュバンを急いで発音すると、ソロバンと聞こえます。シュバンがなまって、ソロバンになったのです」
「中国の人がサンバンと発音すると、ソルバンに聞こえます。それを聞いた日本人がソルバンをソロバンとなまって発音したのです」
なるほど、ソルバン、ソルバンと何度もいっていると、ソロバンになります。
しかし、これはカンボジアから伝来された南瓜が、カンボジア、カンボジア・・・と何度もいっているうちに、カボチャとなまったようなものですね。
算盤は、現代中国語では、スアンパンと発音します。シュンポン、ソンポン、スアンバンと発音する人たちもいます。中国の客家(ハッカ)の人たちはソンパンと発音します。
しかし、算盤の歴史は二世紀までさかのぼれますから、現代中国の発音では当時の発音はわかりません。
文化人類学的に考えれば、いちばん古い中国語の発音を使用しているのは、極東に位置する日本人です。(その証拠に、たとえば、日本人は「仏陀」を原音どおりブッダと読みますが、現代中国人はフォトォと発音します)
そうだとすれば、日本人の使っている呉音・漢音・唐音のなかに、答えがあるのではないでしょうか。
たとえば、「行」という漢字は、呉音ではギョウ(行列)、漢音ではコウ(旅行)、唐音ではアン(行脚)です。ずいぶん音が変わるので、おどろくでしょう。ちなみに、現代中国語では、シンです。
したがって、「算盤」という字がどのように発音されてきたのかを考えますと、時代によって、地域によって、たくさんの発音が存在していたことはまちがいないでしょう。
山田孝雄という国文学の大学者は、ソロバンは、唐音なんじゃないだろうか、と推測しています。
わたしとしては、ジョージ君が旅をすると、フランスではジョルジュ君と呼ばれたり、ドイツではゲオルグ君と呼ばれたりするように、いろいろに発音される「算盤」は日本ではソロバンと呼ばれたのだと考えています。
どんな言語もその国の言葉になるとき、変化を生じるものだからです。
英語では、日本の算盤は「SOROBAN」です。
おもしろいですね。
学院長 筒井保明
吉田松陰とそろばん
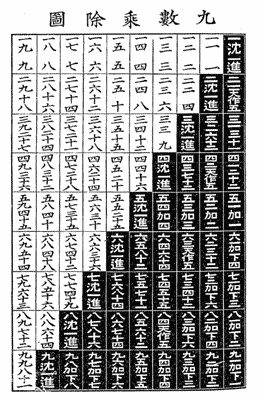
明治維新の精神的指導者であった吉田松陰のことをみなさんは知っていますか。わずか三十年足らずの短い生涯でしたが、現在でも、松陰の志に感動する人たちがたくさんいます。小学生向けの伝記マンガもありますので、ぜひ図書館で借りて読んでみてください。
短い生涯をざっとまとめますと、一八三〇年に、現在の山口県の萩で萩藩士の次男として生まれました。五歳から叔父が開いた松下村塾で指導を受け、九歳のとき、明倫館の兵学師範に就任していますので、早熟な秀才であったといえるでしょう。その後、十一歳で藩主に対する御前講義、十三歳で西洋艦隊撃滅演習。
二十歳のとき、江戸に行き、佐久間象山に師事します。理由は、西洋列強と戦うための西洋兵学を学ぶためでした。
二十二歳で脱藩。水戸や会津や津軽などをまわって江戸にもどりますが、とうぜん、罪に問われました。
一八五三年、ペリー来航。二十三歳の松陰は、来年、ペリーたちが国書の回答を受け取りに来たとき、日本刀の切れ味を見せてやる、と力んでいたようです。
外国留学を決意した松陰は、長崎でロシア軍艦に乗り込もうとするが失敗。
一八五四年、ペリーが再びやってきたので、ペリーの旗艦に小舟を漕ぎ寄せ、勝手に乗り込みました。このとき、日本刀の切れ味を見せようとしたわけではないのですが、アメリカへの渡航を拒否されてしまいます。
下田奉行所に自首、伝馬町牢屋敷に投獄されました。松陰は二十四歳。
その後、死罪を許されて、萩に戻り、幽閉となりました。
一八五七年、叔父から松下村塾を引き継ぎ、若者たちに学問を教えていきます。塾生のなかに、高杉晋作、伊藤博文、山形有朋などがいました。
一八五八年、幕府が天皇の許可を得ずに、日米修好通商条約を結んだことにいきどおった松陰は、過激な行動を計画したり、幕府を強く批判したりしたために、危険人物とされ、ふたたび、幽閉されることになりました。
一八五九年、安政の大獄に連座して、評定の結果、松陰は刑死。二十九歳でした。
松陰の行動だけを見ますと、無鉄砲なようですが、かれが書き残したものを読むと、志の強さに打たれます。
そんな吉田松陰が若者たちに勧めたのが、そろばんと地理でした。松陰は、そろばんの初心者たちのために、「九数乗除図」と題する図を書きました。この図は、松下村塾で配っていたものの写しです。
みなさんも志を持って、そろばんに取り組みましょう。
学院長 筒井保明
そろばんという道具
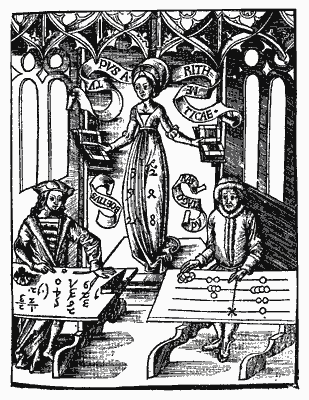
左の木版画のなかの二人の計算する男たちは、筆算で計算する男が、ローマの哲学者、神学者、政治家であったボエチウス(470〜524)、そろばんで計算する男が、古代ギリシアの数学者、哲学者のピタゴラス(紀元前582〜紀元前496)です。
筆算でもたもたしているボエチウスに対して、そろばんを使っているピタゴラスは、おおよそボエチウスよりも千年前の人です。二人の活躍した時代がちがいますから、これは想像によって描かれています。
そういっても、古来、ヨーロッパにおいては西洋型のそろばんが使われていましたから、そろばんを使用するピタゴラスは、あながち絵空事ともいえません。
いろいろな説がありますが、五千年ほどむかし、古代バビロニア人が、ほこりをかぶった板に印をつけて計算したことが、そろばんなどの計算道具の発明につながるスタートであるといわれています。
筆算よりも速く計算できることが大きな利点であり、魅力だったわけです。
その後、「土砂をかぶった板」に代わります。
それから、さらに板に溝を掘って、その溝に数を表す玉を入れて、玉を動かすようにしました。
それを中国人が、玉に軸をとおして動かすようにしました。
さらに日本人が、カバ玉、ツゲ玉のような精巧なそろばんをつくりました。
もちろん、そのあいだにも、紐に結び目をつけたり、算木を並べたりといった計算方法も工夫されていますから、「これもまた一説」というものです。
そろばんの発明後、十七世紀から二十世紀はじめにかけて、道具として、加算機がつくられ、微分解析機がつくられました。機械時計のようにシリンダー、ギア、シャフトなどによって組み立てられています。
現在の電卓やコンピューターは、エレクトロニクス時代のたまもので、そもそも、コンピューターは、電気の計算機、電算機と訳されていたのです。
そろばんのいいところは、暗算を始めるとわかりますが、イメージで操作できることです。目をつぶって、頭の中でそろばんを操作してみてください。かんたんな計算なら、イメージで計算できるでしょう。
いっぽう、加算器、電卓、コンピューターの計算を、わたしたちはイメージで再現することはできません。そもそも中身をイメージすることができません。
そろばん式暗算は、イメージ操作という脳の重要な働きを使うのです。
学院長 筒井保明
右脳開発?

「そろばんで右脳開発!」という言葉を聞いたことがありますか?
「そろばんで頭がよくなる」というのなら、よくわかりますが、「右脳開発」といわれると、わかったような、わからないような…
「右脳開発」という言葉は、どちらかというと、古い言い方です。
一九八〇年代に『右脳革命』という本がベストセラーになりました。脳を左右に分けて、「左脳は言語で考え、右脳はイメージで考える」という説が一般的になったのです。もう四十年ちかくも前の話であり、神経科学もさらに進歩していますから、現在では、「イメージを自分で操作することで頭がよくなる」という言い方がいいでしょう。
なぜなら、脳の左右の分担には、ずいぶん個人差があって、脳の働きを右脳と左脳に分けることは厳密にはできないからです。傾向として、左脳は言語的な働きをつかさどり、右脳は非言語的な働きをつかさどる、というほうが正しいでしょう。
さて、ものごとを身につけるとき、言語から非言語へ、意識から無意識へ、という習得の流れがあります。
たとえば、みなさんが、先生から指示を受けます。ボディーランゲージといって、からだで表現する先生もいるでしょうが、多くの先生は「言葉」で指示を与えます。スポーツでも、芸術でも、習い事でも、まず言葉で説明しますね。そして、多くのみなさんは、左脳でその言葉を聞いて、実際の行動を起こします。
このとき、みなさんは、上手にできるでしょうか。
残念ながら、先生の指示(言葉)を意識しているあいだは、上手にできません。
最初はうまくいかなくても、しばらくのあいだ、同じ動作を続けましょう。すると、だんだんうまくいくようになってきます。動作の全体像(イメージ)が把握できますと、同じ動作が、指示(言葉)がなくても、自然に、無意識に、スムーズにできるようになります。つまり、左脳的な処理から、右脳的な処理に変わるわけです。
一九八〇年代には、まだ「人間は言葉で思考する」という考え方が主流でしたが、現在は「人はイメージで考え、思考を言葉で表現する」という考え方になっています。
相対性理論を発見したアインシュタインも「まずイメージで考え、考えがまとまったら、苦労しながら表示記号に置き換えているのです」といっています。
そろばん(とくに暗算)は、「イメージ操作」(玉の位置の変化がイメージ)の練習です。そういう点では、たしかに右脳的な操作ですから、「右脳開発」といっても、まちがいではないでしょう。
そろばんのスピードは、習熟度に比例します。
学院長 筒井保明
そろばんの夢

そろばんを楽しく練習して、夜、ぐっすり眠ると、起きたときには覚えていなくても、「そろばんの夢」を見ていたはずです。その証拠に、きのう、練習したそろばんがしっかり身についていると思います。
人がなにかを身につけるのは、眠っているあいだです。
睡眠が深くなっていくときに、その日に学んだことを整理し、夢を見る浅い睡眠のときに定着させます。ですから、そろばんが身についたとすれば、この夢を見る浅い睡眠のときに身についたので、「そろばんの夢」というわけです。
もし、みなさんが漢字や英単語を覚えるのが苦手なら、夜、寝る前にさっと復習して、すぐに眠ってしまえばいいのです。すると、眠っているあいだに、「漢字の夢」や「英単語の夢」を見て、朝、起きたときにはしっかり覚えているでしょう。これは、その日の学習のうち、新しいもの、重要なものから、脳は睡眠中に整理・定着するという仕組みを利用するのです。この仕組みはすべてに有効ですから、ぜひ活用してください。
さて、山手学院は、全国珠算教育連盟に加盟していますので、全珠連の検定試験を目標の一つとしています。検定試験の特徴の一つが「スモール・ステップ」。珠算検定試験は級位(一級~十五級)・段位(準初段~十段)を合わせて全三十五段階、暗算検定試験は級位(一級~十級)・段位(準初段~十段)を合わせて全二十四段階になっています。
検定の目標設定は、現在の実力で取得できそうな級位・段位でもいいでしょうし、あるいは、「飛び級」のようにホップ・ステップ・ジャンプで駆けのぼってもいいでしょう。小学生の段位者のほとんどは、後者のタイプですね。
そろばんのヒケツは、中国の思想家である孔子(こうし)がいうように、
『あることを知る人は、あることを好む人にかないません。あることを好む人は、あることを楽しむ人にかないません』
つまり、なんとなくやっている人は、すすんでやっている人ほど上達しないし、すすんでやっている人でも、楽しくやっている人ほど上達しない、ということです。ですから、みなさんは、楽しく、そろばんに取り組んでください。
中国には、三国志の蜀(しょく)の国を建てた三人の英雄の一人、関羽(かんう)が算盤(さんばん・そろばん)を発明したという伝説があります。時期としては、三世紀の初頭です。(算盤の発明は二世紀ごろといわれます)
孔子は紀元前の人ですから、あったとしても、算盤ではなく、算木(さんぎ)でしょう。
計算が楽しければ、算数はかならず得意になります。「そろばんの夢」を見るくらい練習しましょう。
学院長 筒井保明
そろばんは楽しい。

そろばんは手をつかいます。手は脳の運動野のおよそ三分の一、感覚野のおよそ四分の一を占めていますから、手を動かすことの重要さがわかるでしょう。脳の運動野と感覚野にとっては、手は身体の中でいちばん大きな部分なのです。
そろばんを練習して、そろばんが得意になってきますと、そろばんに対応する脳の部位が発達してきます。そろばんができなかった自分とそろばんができる自分は、もうちがう自分です。なにかができるようになると、そのぶん、かならず自分の可能性が広がります。ですから、どんな学習でも、すすんで身につけるようにしましょう。
そろばんと暗算の関係は、そろばんの土台のうえに暗算があります。「意識する・意識しない」にかかわらず、そろばんを習得した人が暗算をするとき、そろばんによって発達した脳の部位が活性化します。同じように、ピアノを習得した人がピアノの演奏を聴くと、ピアノによって発達した脳の部位が活性化しますし、サッカーの選手がサッカーの試合を観戦すると、サッカーによって発達した脳の部位が活性化します。英語では脳の発火(ファイア)といって、カチッと火がつくイメージです。
さて、脳が指令を出してそろばんをはじくわけですが、実際にそろばんをはじくと、その動きが脳によって学習されます。計算する指の動きが運動野や感覚野によって調整され、練習をくりかえすと、速く、正確に、どんどん上達していきます。
音読も同じです。最初はたどたどしくても、なんども声を出して読んでいるうちに、自分の口や舌が運動野や感覚野によって調整されて、じょうずに読めるようになっていきます。じっさい、言語は、自分の声を調整しながら身につけるものですから、日本語にかぎらず、外国語も声を出すことが必要です。
明治時代から、「読み書きそろばん」は、日本人が身につける基本の学習です。音読で声を出すこと、文を手で書くこと、そろばんのたまを指ではじくこと。すべて脳の運動野と感覚野をつかいます。小学生のとき、脳の運動野と感覚野をつかって学習することは、脳の発達にとっても重要なことなのです。見るだけ、聞くだけの受け身の学習ではあまり身につきません。
そろばんは楽しいものです。みなさんがそろばんを練習するときには、ぜひリラックスして、らくな気持ちでおこなってください。かたくなったり、あせったりしたのでは、なかなか上達しません。楽しく練習するのが、そろばん上達のひけつです。
音読やそろばんが得意になると、国語や算数が好きになります。学習は「好きこそものの上手なれ」です。
笑顔で、楽しく、そろばんに取り組みましょう。
学院長 筒井保明