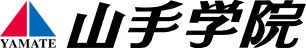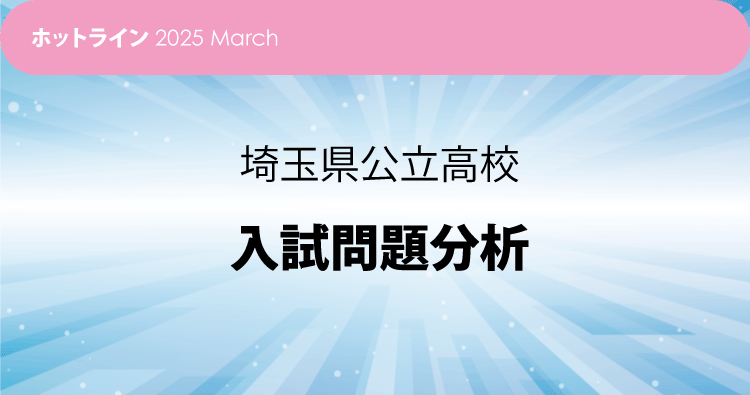
2月26日に実施された埼玉県公立高校入試の問題分析を掲載します。今回は速報版ですので、より詳しい内容につきましては入試報告会や6月ごろに配布予定の進学資料にてご案内します。問題および解答は埼玉県教育委員会のホームページからダウンロード可能です。
≪埼玉県教育委員会:入試問題等のページへ≫
国語 問題分析[速報版]
大問ごとの出題内容に大きな変更はありませんでした。細かいところでは、大問2の文法問題2題が、話し合いに関する問題に組み込まれるという出題形式の変更がありましたが、大きな影響はなかったでしょう。
大問1の小説は、河邉徹著「ヒカリノオト」(ポプラ社・2024年5月)からの出題でした。文字数は約3,600字、設問の多くは登場人物の様子や心情の把握に関する問題です。
大問2は漢字・知識・話し合いに関する問題。漢字の出題のうち、(1)の「簡潔」は平成29年度入試の書きの問題で、(4)の「ホウソウ(包装)」は平成22年度後期入試の書きの問題でそれぞれ出題されたことがあるものです。話し合いに関する問題に組み込まれた文法は、(1)が動詞の活用形、(2)は敬語に関する出題でした。
大問3の説明的文章は、奥野克巳著「ひっくり返す人類学 生きづらさの『そもそも』を問う」(ちくまプリマ-新書・2024年8月)からの出題でした。文字数は約3,000字、例年より読みやすい文章でした。2題出題される記述問題の字数が例年よりも減っていることと、問題の難易度もそれほど高くなかったため、全体の平均点は例年よりも上がると思われます。
大問4は和歌を含む古文の読解。かなづかい、動作主、内容把握と例年通りの出題内容ですが、問2の記述問題は本文全体が読めていないと書けなかったのではないかと思います。
大問5は「食品ロスの削減のためにわたしたちができること」について、資料の読み取りと体験をふまえた自分の考えを書く作文でした。よくあるテーマでしたので、事前に類似問題を練習した人も多かったと思います。
数学 問題分析[速報版]
学力検査問題・学校選択問題ともに大問1は小問集合、大問2は作図と証明、大問3は会話文問題と変化はなく、今年度は大問4に関数が選ばれました。学校選択問題のみ大問5として図形が出題されています。配点などには大きな変更はありません。難易度も大きな変化はありませんでしたが、高難易度の問題が少なかったので、数学が得意な受検生にとっては少し解きやすく感じたかもしれません。
昨年度から途中説明を書きながら解答する問題が出題されなくなりましたが、今年度も解法説明を求める問題は出題されていません。かわりに、今年度では中2で学習する式の計算の記述問題が出題され、昨年度より記述する文量は多くなっていました。
大問1の最後に出題される記述問題は今年度もデータの分析に関する問題が出題されています。毎年必ず出題されている単元ですが、最近は特に記述問題で出題されているので、読み取り方など深い理解が必要になるでしょう。
大問3の会話文問題は共通の問題になっています。関数や場合の数など様々な分野から出題されますが、今年度は規則性の問題でした。会話内容を読み解くことが出来れば比較的得点を取りやすい単元なので、しっかりとした練習が必要です。
大問4は年度によって出題される単元が変わります。学力検査問題では図形、学校選択問題では関数か場合の数であることが多いです。どのような問題が出題されてもいいように、時間配分にも気を付ける必要があるでしょう。
社会 問題分析[速報版]
一部を除き、出題形式に変化はありません。全体を通じて頻出問題が並んでおり、社会の対策を入念に行ってきたかどうかが問われるものになっています。
大問1:世界地理については、世界の特色ある地域、資料解釈に関する問題が出題されました。例年の入試と同等の難易度で、学習をしてきた受検生であれば問題なかったと思われます。
大問2:日本地理について、扇状地、日本の気候は頻出内容となっており、これらも対策をしてきた受検生であれば問題なかったはずです。問3はデータからどの県かを考える問題で、標準的な難易度です。
大問3:歴史(古代~近代)について、こちらも頻出の問題から構成されており、対策をしていれば正答できるものとなっています。
大問4:歴史(近代~現代)について、問3はあるテーマに基づいて歴史上の出来事を起きた順に並べたステップチャートに関する問題です。他県では既に出題されたことがある形式の問題が、今回埼玉県の公立高校入試で出題されました。歴史上の流れを把握していたかが問われる問題です。その他は標準的な問題となっています。
大問5:公民総合について、問2は衆議院の優越について正しい内容の選択肢をすべて選ぶ問題です。衆議院の優越については内容が多くて混同しやすいため、ここで差が出てくるものと思われます。問5は何らかの要因により需要曲線・供給曲線が左右に移動することによる価格の変化を問う問題です。需要曲線・供給曲線がなぜどのように移動するのかを理解していないと誤った選択肢を選んでしまうおそれがあります。
大問6:地理・歴史・公民融合問題については、いずれも標準的な問題となっています
理科 問題分析[速報版]
大問の構成や配点は例年通りで、大きな変更はありませんでした。全体的には基本事項に関する問題が多く、例年より平均点は高くなると思われます。
大問1は小問集合で、4分野からそれぞれ2題ずつ出題されています。問4の「ばねの並列つなぎ」はあまり見慣れない問題でしたが、その他は基本的な知識を問う問題でした。
大問2は大地の変化に関する問題で、断層や震度、プレートの動きなどについて出題されました。断層の仕組みや震度の最小値と最大値、海溝など細かい知識を問う問題が出題されました。また、震央の位置を求める作図の問題が出題されました。
大問2は生態系に関する問題で、菌類や細菌類など分解者のはたらきなどについて出題されました。実験結果が異なる理由や指定語句のある記述問題など読解力を必要とする問題もありましたが、例年よりも解きやすかったと思います。
大問3は密度に関する問題で、プラスチックの性質や液体に入れたときの浮き沈みなどについて出題されました。昨年に続き、正しい選択肢をすべて選ぶ問題が出題されました。今後も出題される可能性があると思われます。また、読解力を必要とする、湖の底の方の水は凍らない理由について考察する問題が出題されました。
大問5は電流と磁界に関する問題で、抵抗の大きさや電流がつくる磁界などについて出題されました。基本的な問題がほとんどでしたが、地球の磁界の強さや向きについての見慣れない内容からの出題もありました。
英語 問題分析[速報版]
埼玉県の公立入試の英語は、学力検査問題と学校選択問題の2種類があり、学校選択問題は難関公立高校を中心に22校が採用しました。
学力検査問題は、大問構成や配点・出題形式に昨年度と変化はなく、受検生は練習してきた通りの時間配分や問題の解き方で取り組むことができたと思います。難易度についても大きな変化は見られませんでした。
学校選択問題は、大問2が1問増えたことで配点も4点増加し、一方、大問3は配点が4点減少しました。大問2で新たに加わったのは、解答を日本語で記述する形式の問題でしたが、学力検査問題と同じもので、難易度は高くありませんでした。大問3では、受検生が最も苦労していた、2語補充による要約文の完成がなくなり、その代わりに本文の内容一致問題が出題されました。形式は「本文に一致するものをすべて選ぶ」というもので、文章をすべて読み終えていなければ解けないものになっていました。文章の語数や難易度は、昨年までとほとんど変化はありませんでしたが、設問は比較的取り組みやすい問題が多く、平均点は上がると思われます。
今回、全体を通して難易度に大きな変化はありませんでしたが、今後は、語彙数の増加・長文化・リスニングの高速化が予想されます。これから受検生になる皆さんは、強い語彙力や文法力に基づいた『読解力』『作文力』『リスニング力』が要求されますので、ReadingやListeningによる英文のインプット、SpeakingやWritingによるアウトプットに努めましょう。