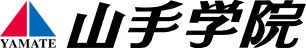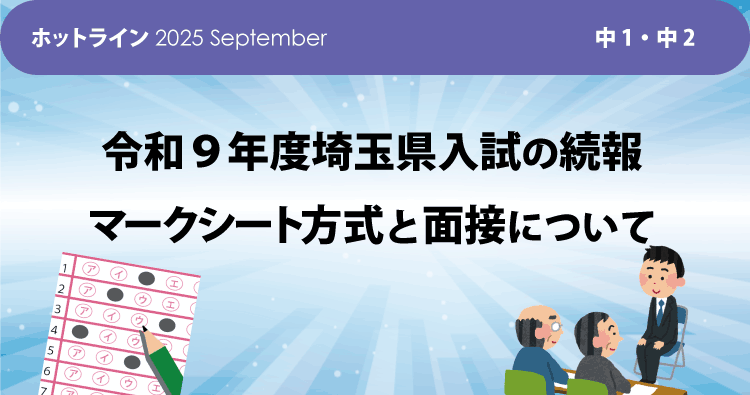
先月のHOTLINEに続き、令和9年度埼玉県公立高校入試の続報です。
埼玉県教育委員会から、8月18日にマークシート方式導入についてのリーフレットが、8月29日には面接についてのリーフレットが公開されました。今回は、それぞれのリーフレットの内容について見ていきます。なお、リーフレットのデータは埼玉県のウェブサイトで公開されていますので、興味のある方はご参照ください。
■ 学力検査問題におけるマークシート方式導入についてのリーフレット(PDF:767KB)
■ 面接についてのリーフレット (PDF:2638KB)
上記PDFファイルは埼玉県教育委員会の下記ページよりダウンロードされます。
≪令和9年度埼玉県公立高等学校入学者選抜に関する情報≫
■マークシート方式導入についてのリーフレット
今回のリーフレットには、「マークシートの解答用紙の例」、「学力検査問題の例と解答例」、「学力検査問題についてのQ &A」が掲載されています。
マークシートの解答用紙については、特別な書式のものではなく、マークする場所を間違えないように事前に練習をしておけば特に心配することはなさそうです。学力検査問題の例についても、7月24日に公表されたものと同じでしたので、特に新しい情報はありませんでした。
一方で、Q &Aには、7月公表の内容にはなかった英作文や数学の作図に関する質問がありましたので、ここで取り上げておきます。(Q「英作文、数学の作図は、出題されるのか。」)
7月に公表された解答用紙のサンプルには、英語の解答用紙はなく、英作文の出題の有無は解答用紙のサンプルをヒントに考えることはできませんでした。また、数学の解答用紙のサンプルは、左側にマークシート欄、右側には記述式欄があり、記述欄は1つめが「説明」、2つめが「証明」と書かれていました。あくまでサンプルですが、少なくとも作図の解答欄はありませんでしたので、作図はどうなるのか、と思った人もいたことでしょう。作図が出題されないとは限らないため、この質問は重要です。
この質問に対する回答は、「学力検査問題の詳細に触れる内容になるため、国語の作文、英語のリスニングを除いて、出題する、しないは、申し上げられません。」とのことでした。
事前に、得点の配分は、「マークシート方式の問題が9割程度、記述式の問題が1割程度」と公表されています。ここで英作文の出題や数学の作図の出題に言及すると、記述式の問題1割の内訳がわかってしまいかねません。したがって、現時点で回答できる内容ではないのでしょう。また、「数学で、コンパスや三角定規については必要になるのか。」という別の質問に対しても、「令和8年10月頃に公表する『受検者心得』等でお知らせする予定です。」という回答でしたので、出題内容の詳細がまだ決まっていないとも考えられます。
過去に学校選択問題が導入されたときには、事前に公表されたサンプル問題と実際の入試問題の違いに多くの関係者が驚いたといったことがありました。現時点で受検生(現中2生)が出題内容を予想してもあまり意味はありません。何が出題されても問題ないように準備を進めておくことが大切です。
■面接についてのリーフレット
8月29日には、面接についてのリーフレットが公表されました。こちらも事前に公表されていた内容が多くを占めますが、面接のねらいや概要、評価について丁寧に説明されています。一読しておくとよいと思います。
今回のリーフレットでは、面接当日の流れについての詳しい内容が公表されました。
《面接当日》
[形式]
個人面接 又は 集団面接 (形式は各高校が決め、選抜実施内容で公表されます。)
[流れ]
入室 → My Voice(マイボイス) → 質問・応答 → 退室
「My Voice」とは、面接の冒頭で行う自己PRの時間のことです。これまでの経験や力を注いだこと、将来取り組みたいことなどを自分の言葉で表現し、伝える時間です。1人あたり1分30秒~2分程度が割り当てられます。
My Voiceのあとは、My Voiceで表現した内容に対して、面接委員(2人以上)が質問をします。時間は1人当たり3分30秒~6分程度です。面接委員は、受検生の考えや思いの背景を問う質問を行いますので、その質問に対して、自分の言葉で、さらなる自分の思いや考えなどを答えていきます。リーフレットには、「上手く答えることよりも、自分なりに考え、伝えることが大切です」と記載されています。したがって、自己理解を深め、今までの自分の経験を深く掘り下げて考える練習をしておく必要があるでしょう。
評価については、事前に公表されていたとおり、共通の観点が2つ、学校独自の観点が1つ、合計3つの観点について、「3~5」の3段階で評価されます。
面接に向けて今できる準備は、いろいろな経験をしておくことです。その経験は特別なものである必要はありません。部活動、委員会活動、校外活動、日頃の学習など、何でも構いません。実績そのものが評価されることはありませんが、「それまでの過程(プロセス)や意欲、身についた力、学びに向かう姿勢などを評価します」と書かれていますので、日常の学校生活を大切にすることが、面接対策にもつながるでしょう。