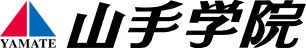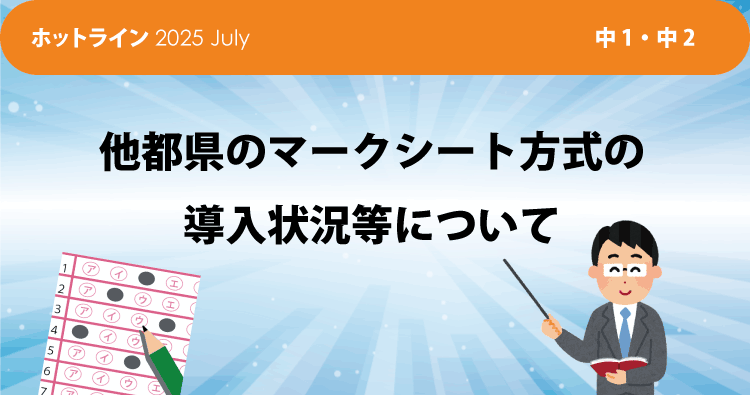
7月24日に令和9年度公立高校入試よりマークシート方式を導入することを埼玉県が公表しました。
今回は、他都県のマークシート方式の導入状況とその後の変化についてお伝えしたいと思います。
■マークシート方式の導入の背景
東京都や神奈川県、千葉県では、埼玉県に先行して公立入試でマークシート方式を導入しています。実は、これらの都県では採点ミスが相次いで発覚し、本来合格していた人が採点ミスのために不合格になるという事態が起きていました。そこで採点ミスへの対策として、東京都は平成26年度実施入試においてモデル校20校でマークシート方式を実施、平成28年度入試からすべての学校で導入しました。なお、神奈川県は平成29年度入試から、そして千葉県は令和6年度入試からマークシート方式を導入しています。ただし、全ての問題がマークシート方式になったわけではなく、記述式の解答を求める問題も引き続き出題されています。令和9年度から導入する埼玉県も、9割が記号選択式、1割が記述式で出題という発表でした。
埼玉県からはこれまでに採点ミスに関する発表はありません。しかし、他都県で採点ミスが頻発した背景には、採点期間の短さや長時間の採点による担当者の疲労などが挙げられており、埼玉県でのマークシート導入は時間の問題と見られていました。
■マークシート方式導入後の変化
先行してマークシート方式を導入した他都県の状況を見ると、出題傾向自体には大きな変化は見られません。仮に出題傾向が大きく変わるとすれば、学習指導要領が改訂されるタイミングでしょう。したがって、解答形式が変わるからといって、出題傾向まで変わるのではないかと心配する必要はありません。
一方で、記号選択式の出題数や問題の形式には変化が見られます。東京都と神奈川県の社会科の出題状況を例に見てみましょう。
〈東京都:社会〉
平成26年度(マークシート方式導入前):記号選択式13問 記述式7問
令和7年度 (マークシート方式導入後):記号選択式17問 記述式3問
東京都は記号選択式の出題が増えているのがわかります。どの問題も選択肢は4つですが、組み合わせがすべて合っていないと正答にならない問題が多く出題されています。(2つ合っていないと正答にならない問題が3問、4つ合っていないと正答にならない問題が5問。)また、各選択肢の文が長いものが多いことも特徴的です。そして、記述問題では地理・歴史・公民のそれぞれの分野で1問ずつ、合計3問出題されています。解答の長さは80~90字程度と比較的長いのが特徴です。
〈神奈川県:社会〉
平成28年度:記号選択式の選択肢の数 最大で6つ(マークシート方式導入前)
令和7年度 :記号選択式の選択肢の数 最大で8つ(マークシート方式導入後)
※選択肢6つの問題が8問、8つの問題が3問。
神奈川県の場合は選択肢の数が増えており、令和7年度入試では8つの選択肢から答えを選ぶ問題が3問出題されています。なお、令和6年度入試では9つの選択肢から答えを選ぶ問題が出題されていました。これだけ選択肢があると、正確な知識はもちろん、資料を読み取る力や高い考察力が求められます。
注意してほしいのは、マークシート方式に変わるからといって、単に知識を詰め込めば高得点が取れるわけではないということです。問題の解決に必要な根本的な力は変わりません。マークシート方式になっても、これまで同様に知識や技能、思考力、判断力を確かめる問題が出題されます。大切なのは、新しい解答形式に合わせて、これらの力を効率的に伸ばす対策を早めに始めることです。
変化のときこそチャンスです。万全の状態で受検を迎えられるようにしましょう。