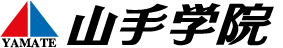埼玉県の公立高校の入試制度
埼玉県の公立高校入試のうち、学力検査は2月末に実施されます。国語・数学・社会・理科・英語の5科目で、各科の配点は100点満点です。平成28年度までは、国語・数学・英語が50分、理科と社会は40分で実施されていましたが、平成29年度からは、理科・社会も50分で実施されています。また、数学と英語で応用問題を含む「学校選択問題」を実施することができるようになっています。学校選択問題を実施する学校は毎年1学期に発表されます。
なお、令和5年10月16日に埼玉県から「埼玉県公立高等学校入学者選抜方法の改善について」の素案が公表され、県民コメント期間を経て12月21日に決定内容が公表されました。令和6年度に中学1年生になる皆さんが高校入試を迎える際には、「共通選抜」と募集の一部で実施することができる「特色選抜」の導入、「調査書」の様式の変更、「自己評価資料」の提出とそれにもとづく面接の実施など、大きな変更が予定されています。
令和7年度 入学者選抜日程
| 出願入力期間(インターネットを活用した出願を実施) | 1/27(月)~2/10(月) |
|---|---|
| 出願書類等の提出期間 | 2/13(木)、14日(金)、17日(月) 2/13は郵送による提出 |
| 志願先変更期間 | 2/18(火)、19日(水) |
| 学力検査 | 2/26(水) |
| 実技検査(芸術系学科等)、面接(一部の学校) | 2/27(木) |
| 追検査 | 3/3(金) |
| 入学許可候補者発表 | 3/6(木) |
※令和6年度入試では、入学許可候補者発表日の後に追検査が実施されましたが、令和7年度は追検査実施後に入学許可候補者が発表されます。
□志願先変更
志願者は、指定された期間内に1回に限り、志願先を変更することができます。同一校の学科間や第2志望(第2志望に準ずる志望を含む)についても変更ができます。
ただし、一般募集による入学者選抜に出願した人は、帰国生徒特別選抜または外国人特別選抜の出願資格を有していても、帰国生徒特別選抜または外国人特別選抜へ志願先変更をすることはできません。
□併願
県公立高等学校及び県立特別支援学校2校以上に「入学願書」を提出することはできません。また、同一高等学校における全日制課程と定時制課程の双方に「入学願書」を提出することはできません。
□追検査
インフルエンザ罹患をはじめとするやむを得ない事情により学力検査を受検できなかった志願者を対象に実施されます。追検査は、国数英理社の5教科で実施され、数学と英語の学校選択問題も用意されています。面接・実技検査は実施されません。(不登校の生徒などを対象とした特別な選抜、帰国生徒特別選抜による募集、外国人特別選抜による募集、定時制の課程における特別募集においては、面接が実施されます。)
追検査の入学許可候補者は、原則、募集人員の枠外で決定されます。
選抜
「学力検査」および「調査書」に、各高校の判断で「面接」や「実技検査」を加え、全項目を点数化した合計得点の順位にしたがって合否判定をする、「加算方式」で選抜が行われます。
合否の決定方法について
選抜は第1次選抜・第2次選抜・第3次選抜と最大3段階で実施されます。第3次選抜を実施するかどうかは各高校が定めます。
第1次選抜では募集人員の60~80%を入学許可候補者として決定し、第2次選抜では残りの20~40%を入学許可候補者とします。さらに残りの人員を第3次選抜で入学許可候補者とします。
選抜方法
□第1次選抜
「学力検査の合計点」と「調査書の合計換算点」の比率が、6:4(学力重視)~4:6(調査書重視)の範囲内になるように、「調査書の合計点」に各高校が定めた係数を乗じ、換算点を算出します。合計得点の高い順に入学許可候補者が決定されます。
事前に自己申告書を提出した不登校の生徒などを対象とした特別な選抜も、第1次選抜で実施されます。
□第2次選抜
「学力検査の合計点」と「調査書の合計換算点」の比率が、7:3(学力重視)~3:7(調査書重視)の範囲内になるように、「調査書の合計点」に各高校が定めた係数を乗じ、換算点を算出します。合計得点の高い順に入学許可候補者が決定されます。
【第2志望について】
第2志望が認められている学科・コース等では、当該学科・コース等の第2次選抜の際に、第2志望者を含めて選抜されます。
【第2志望に準ずる志望の選抜について】
すべての学科・コース等の選抜を終えたのちに実施されます。なお、選抜は、選抜対象者が募集人員より少ない学科・コース等のみで実施されます。
□第3次選抜
第1次選抜や第2次選抜で入学許可候補者とならなかった者のうち、各高校で定めている一定以上の順位の者を対象として実施されます。第3次選抜を行わない高校もあります。
第1次選抜または第2次選抜における一定以上の順位の者を対象に、「特別活動等の記録の得点」、「その他の項目の得点」、「その他の資料」から1つまたは2つ以上の組み合わせなどを用いて選抜します。その際には、通学距離または通学時間を資料として用いることができます。
□川越市立高等学校の「地域特別選抜」
川越市立川越高等学校では、募集人員の10%程度の範囲内で、川越市立中学校に在籍する生徒及び川越市内に在住する生徒を対象に「地域特別選抜」が実施されます。
地域特別選抜の対象分野は次の通りです。
- 学習・部活動・生徒会活動等で優れた実績又は資質を持っている者。
- 文化・スポーツに秀で、模範となる逸材であり、入学後も継続できる者。
出願にあたっては、入学願書、受検票以外に、「地域特別選抜志願書」と「出願資格証明書」が必要です。
得点化される具体的内容
□学力検査
令和7年度の学力検査は2月26日に実施されます。国語・数学・社会・理科・英語の順に各50分の検査時間です。配点は各教科100点満点です。また、英語ではリスニングテストが含まれ、国語は作文も出題されます。外国語科や理数科等の専門学科においては、該当科目で傾斜配点を行うことがあります。
□調査書
以前は「調査書」というと、「学習の記録の得点(内申点)」のみ、明確に点数化されていましたが、現在では「特別活動の記録」や「その他の項目」についても評価基準がはっきりと示され、点数化されています。
①「学習の記録の得点(内申点)」
各学年の学年評定に各高校が定める学年別の比率をそれぞれ乗じて加えた点数で表します。各学年の学年評定は9教科5段階評価で合計45点満点です。例えば「1年:2年:3年」の比率が「1:1:3」だとすると、「学習の記録の得点(内申点)」の最高点は、45×1+45×1+45×3の計算結果である、225点となります。
②「特別活動の記録」
学級活動、生徒会活動、学校行事その他について、各高校が定めた基準にしたがって点数化し、加算されます。
③「その他の項目」
総合的な学習の時間の記録などについて、各高校が定めた基準にしたがって点数化されます。英語検定や漢字検定などの資格や、出欠の記録なども対象になる場合があります。
以上①~③の得点の合計が「調査書の得点」となります。なお、②と③の得点の合計が①を超えることはありません。
実際の選抜では、「学力検査の得点」(500点)と「調査書の得点」の比率が、第1次選抜で6:4~4:6の範囲で、第2次選抜では7:3~3:7の範囲に収まるように調整しなければならないという規定がありますので、調査書の合計得点に一定の係数をかけることになります。
□面接
面接の実施については、各高校の裁量で決定することができます。面接を実施する場合は、各高校の定める基準にしたがって得点を算出し、「その他の資料」として加算されます。なお、実技検査を実施する場合は、面接の実施はありません。
□実技検査
芸術系学科・体育系学科では、実技検査を実施します。実技検査の評価は、各高校が定める基準にしたがって得点を算出し、「その他の資料」として加算されます。また、外国語系学科では、英語による問答等を1人につき5分程度実施することができます。
選抜基準の例
《A高校の選抜基準》
| 学力検査の扱い | 500点 | |
| 調査書の扱い | 学習の記録の得点(1:1:3)……225点 特別活動等の記録の得点 …… 90点 その他の項目の得点 …… 20点 |
335点 |
●第1次選抜(80%を入学許可候補者とする)
学力検査:500点 調査書:335点 その他:実施しない 合計:835点
●第2次選抜(18%を入学許可候補者とする)
学力検査:500点 調査書:215点 その他:実施しない 合計:715点
●第3次選抜(2%を入学許可候補者とする)
第2次選抜における合計得点の一定の順位の者を対象に、特別活動等の記録の得点、その他の項目の得点で選抜する。
《解説》
A高校の選抜基準では、第1次選抜は学力検査:調査書がほぼ6:4、第2次選抜はほぼ7:3となり、学力を重視した選抜基準となっています。なお、第2次選抜の調査書の得点は、素点335点に対して0.64を乗じた数になります。また、第3次選抜は、第2次選抜の合計点の一定の順位以上の者が対象となり、合否の判定は特別活動等の記録の得点とその他の項目の得点で実施されます。
□得点の算出例
A高校の選抜基準を例に、得点を算出してみます。(特別活動等の記録の得点とその他の項目の得点はわかりませんので、計算には入れません。)
case①: 学力検査点 325点 内申 中1:31 中2:31 中3:35
case②: 学力検査点 315点 内申 中1:32 中2:31 中3:36
case③: 学力検査点 304点 内申 中1:36 中2:35 中3:40
学力検査点だけで見てみると、①→②→③の順位になります。case①とcase③の差は21点もあります。
実際の合否の判定では、選抜基準にもとづいて調査書が得点化され、学力検査点に加算されます。
第1次選抜および第2次選抜基準にもとづいて点数を算出すると、次のようになります。
《選抜ごとの換算点》
case①: 第1次選抜得点 492点 第2次選抜得点 432点
case②: 第1次選抜得点 486点 第2次選抜得点 424点
case③: 第1次選抜得点 495点 第2次選抜得点 426点
学力検査点だけでみると、得点の高い順に①→②→③となりますが、選抜基準にもとづいて点数を算出すると、第1次選抜では③→①→②、第2次選抜では①→③→②となります。
A高校の第1次選抜では、学力検査の得点と調査書の得点の比率がほぼ6:4ですので、第2次選抜と比べると、内申が高い人が有利になります。上記例の場合、case③は当日の学力検査点は最も低いですが、内申が高いため、換算すると1位となります。
A高校の第2次選抜では、学力検査の得点と調査書の得点の比率がほぼ7:3ですので、当日の学力検査点で高得点がとれた人の方が有利になります。上記例の場合は、最も学力検査点が高いcase①が1位になっています。ただし、2位は内申が高いcase③がcase②の換算点を上回る結果となっています。
山手学院では、数万件に及ぶ過去の受検生たちのデータを詳細に分析し、進学指導や志望校決定の際の参考資料、直前期の過去問指導に役立てています。例えば、過去問指導の際には、中1~中3の学年評定に基づき、志望校の合否ラインと目標点を年度ごとに算出し、どの教科でどれだけ得点すればよいか、具体的な数値目標を示して指導しています。
埼玉県の私立高校の入試制度
埼玉県の私立高校の入試解禁日は例年1月22日です。他校の併願日程などを踏まえ、入試を複数回実施しているところがほとんどです。大半が1月中の入試で合格者を確定させます。
現在、県内の私立高校のうち、浦和明の星女子を除くすべての高校が、高校からの募集を行っています。
なお、埼玉県の私立高校では、東京都や神奈川県、千葉県などで実施されている、「公立中学校を通した入試相談」を実施していません。したがって、受験生は、各高校が主催する「個別相談会」に参加し、通知表や会場テストの結果、各種検定などの資料をもとに、合格の可能性について相談しておく必要があります。
山手学院では、11月下旬に各私立高校の入試担当の先生方に集まっていただき、合格の可能性について受験生・保護者と高校の先生が、直接相談できる進学イベント「個別相談会」を実施しています。高校主催の相談会と同じ内容ですので、相談内容は入試結果にそのまま反映されます。数週間かけて、何校もの高校に何度も足を運ばなくても、受験する可能性のある高校の個別相談を1日で済ますことができます。(塾生のみ参加できます。)
推薦入試と一般入試
□推薦入試(埼玉県)
埼玉県内の私立高校入試は、「内申(通知表)」や「会場テストの偏差値」などの選抜基準をもとにした「推薦入試」を中心に実施されています。
各私立高校は、夏から秋にかけて入試日程や単願・併願の推薦基準などを明記した「入試要項」を発表します。その後実施される個別相談で、受験生の通知表や会場テスト偏差値、各種検定などの資料をもとに、生徒・保護者と私立高校との間で合格の可能性などが検討されます。
推薦は、大きく分けて「学校推薦」と「自己推薦」があります。どちらの推薦で出願するかについては、各高校の個別相談会の際に相談してください。入試担当の先生が丁寧に教えてくれます。
「学校推薦」は、通っている中学校から推薦をもらう必要があります。中学校が推薦できる基準は「内申」です。各私立高校が設定する「内申(通知表)」の基準を超えていれば、推薦を受けることができます。通っている中学校の担任の先生を通して推薦書を書いてもらい、出願時に提出します。
「自己推薦」は、各私立高校が設定する「会場テストの偏差値」の基準を超えていることが条件になります。中学校の推薦は必要ありません。出願の際には、受験生本人や保護者が記入した「自己推薦書」を提出する場合があります。
※他にも、推薦基準には「欠席日数」や「成績に1・2がないこと」などがあります。
□一般入試(埼玉県)
推薦基準は特になく、入試当日の学力試験の結果に重点を置いて選抜が行われます。推薦基準がないため、原則として「個別相談」は実施されません。
慶應義塾志木、早稲田大学本庄高等学院、立教新座など難関大学の附属高校は、推薦入試よりも一般入試に重点を置いた生徒募集を行っています。
単願・併願
□単願
合格したらその高校へ入学することを前提に出願する入試です。学校によっては「専願」という場合があります。事前に高校から提示された出願資格を満たす必要があります。1人1校しか出願することはできません。当然ですが、公立高校の志願者は受験できません。作文や面接、簡単な適性検査を実施する場合や、3教科の入学試験を実施する場合があります。
□併願
合格発表後、他校の入試結果がわかるまで入学手続きを保留できる入試です。単願より基準が厳しくなるのが一般的です。入試日程さえ重ならなければ何校でも受験できます。公立高校の志願者も受験できます。
東京都の私立高校の入試制度
東京都の私立高校の入試解禁日は推薦入試と一般入試で日程が違います。推薦入試は例年1月22日以降実施されています。一般入試は2月10日以降に実施されています。
東京都の私立高校の入試は、埼玉県とルールが異なります。埼玉県では、現在のところ「公立中学校を通した入試相談」は実施されていません。一方で、東京都では、七都県高校進学問題協議会における協議を経て、私立高校と東京都中学校長会で合意した日以降(例年12月15日)に、「公立中学校を通した入試相談」が実施されています。ルール上、合格の可能性を述べるにとどめ、確約、内定は行われません。また、「公立中学校を通した入試相談」の際に用いる資料は、中学校3年間の学習の記録や特別活動の記録、出欠の記録などで、偏差値資料は用いません。
埼玉県の中学校との入試相談は、東京都内の私立高校についても行われていません。したがって、都内の私立高校の受験を希望する場合は、受験生個人が、各高校で実施される入試説明会等に参加し、個別相談を受けておく必要があります。(一般入試には「併願優遇」の制度があり、優遇を受ける場合も相談が必要です。)
推薦入試と一般入試
□推薦入試(東京都)
受験する私立高校が第一志望であり、在籍する中学校長の「推薦状」がもらえ、各私立高校が決めている推薦基準に該当することが受験の条件です。例年1月22日以降に実施されます。原則として、入試相談を行ったうえで出願する必要があります。埼玉県の中学生は中学校を通した入試相談がありませんので、個別に動く必要があります。
選抜は「書類選考」「作文」「面接」「実技」「適性検査」の中から、各私立高校が自由に選んで実施します。「適性検査」については、国語・数学・英語の3教科を、一般入試よりも短い時間で実施する場合が多いようです。
□一般入試(東京都)
東京都の私立高校の一般入試には、「併願優遇を利用した一般入試」と「併願優遇を利用しない(併願優遇がない)一般入試」があります。一般入試は例年2月10日以降に実施されます。
《併願優遇を利用した一般入試》
国立や公立高校を第一志望とする生徒を対象にした制度です。志望する私立高校が設定した内申の基準をクリアし、「公立中学校を通した入試相談」において、併願優遇の利用が私立高校との間で確認されていれば、一般入試において「併願優遇」の制度を使うことができます。優遇の内容は学校によって違いますので、入試説明会や個別相談会で確認してください。
「公立中学校を通した入試相談」がない埼玉県の中学生は、自分で各高校の個別相談会に参加し、入試相談を受けておく必要があります。
《併願優遇を利用しない一般入試》
併願優遇の基準に届かない場合や、そもそも優遇の制度がないといった場合は、優遇を受けずに受験することになります。試験当日にどれだけ得点できたかで結果が決まります。